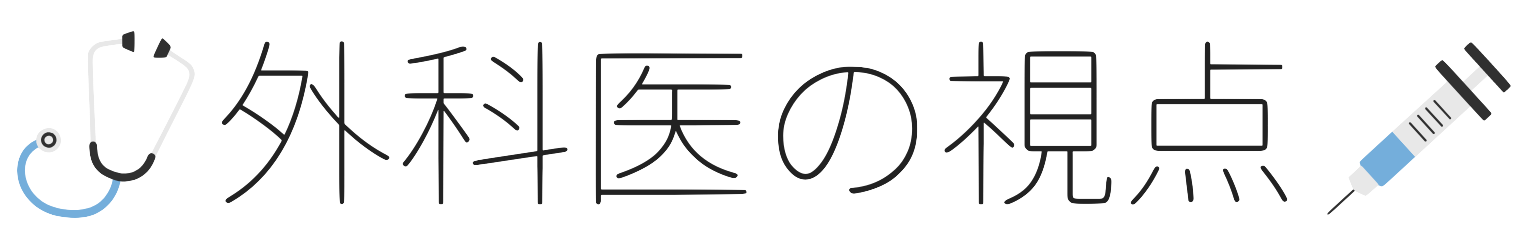「アライブ がん専門医のカルテ」は、フジテレビ系「木曜劇場」で1月から放送されている医療ドラマです。
現代のがん治療をリアルに表現しつつ、医療過誤を取り巻く医師たちの複雑な人間模様を描き出すミステリーは目の離せない展開になっています。
さて、2月13日放送の第6話では、抗がん剤治療をやめて民間療法を希望する若い胃がん患者さんが登場します。
抗がん剤を勧める腫瘍内科の恩田医師(松下奈緒)に対し、患者さんの父親は、
「うちの母親も知り合いもみんな抗がん剤をやって苦しんで結局死んでいった」
「抗がん剤は毒だ」
と言い、娘に抗がん剤治療を受けさせたくないと主張します。
恩田医師は抗がん剤治療を中心とした「標準治療」の有用性を誠実にデータで説明しようとしますが、かえって反発を受け、逆効果でした。
患者さんとご家族は民間療法クリニックを受診し、その治療を魅力的に感じます。
のちに、このクリニックは「がんが消える効能がある」と謳った高額なサプリメントを販売していたことで摘発されてしまいました。
これは、実際の医療現場においても時に起こる重要な問題です。
医師と患者さんとの間でがん治療に対する考え方がすれ違い、
「医師が最も受けてほしいと思う治療を患者さんが拒否してしまう」
というケースは少なくないのです。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
がん治療に対する考え方のすれ違い

医師は当然ながら、目の前の患者さんに最も有効な治療を提供したい、と考えます。
そして患者さんも同様に、最も有効な治療を受けたい、と考えるでしょう。
ここにすれ違いはないはずです。
ところが、「有効な治療」に対する考え方は、医師と患者さんとの間で一致していないことがあります。
医師にとって「最も有効な治療」とは、
「目の前の患者さんと同じがんの患者さんをたくさん集めた時に、最も多くの人に効く治療」
のことです。
つまり、
「100人中50人に効く薬より60人に効く薬を投与したい、80人に効く薬より90人に効く薬を投与したい」
と考えています。
同じ種類のがんでも、患者さんによってその「振る舞い」や「顔つき」は多種多様です。
「100人中100人のがんに効く薬」はありません。
たとえ抗がん剤の開発がおびただしい速度で進み、その種類が年々増えていても、です。
ですから、「少しでも多くの割合の人に効く薬を」と医師は考えているわけです。
「効く」とはどういう意味か?

では、そもそも医師が考える「効く」とはどういう意味でしょうか?
手術で切除してしまえる比較的初期のがんは別として、完全に切除するのが難しい進行したがんの場合、抗がん剤だけでがんが消えてしまうことはまれです。
よって薬ががんに「効く」というのは、医師にとっては、
「患者さんが(時にがんを持ちながら)より長く生きられる」
ことを指します。
つまり、医師は原則、
「より多くの人が、より長く生きられる治療」を最も「効く」治療とみなしている
というわけです。
すると、どの治療が最もよく「効く」のかを知りたい、ということになりますね。
どのように調べればいいのでしょうか?
臨床試験が科学的根拠(エビデンス)を作る

その答えが「臨床試験」です。
例えば、同じがんで同じ進行度の患者さんを1000人集め、500人ずつのグループに分け、それぞれに薬Aと薬Bを投与する。
どちらがどのくらいの割合で効くか(奏功率)や、どちらがどのくらい長く生きられるか(生存率)を測定するわけです。
こうした臨床試験は世界中で絶えず行われています。
その結果が蓄積し、現時点で最もよく効くことが判明した治療を「標準治療」と呼びます。
ここで「標準」とは、「普通」ではなく「最良」を意味します。
「世界標準」「世界的なスタンダード」という語意です。
では患者さんの方は、治療が「効く」ことをどう捉えているでしょうか?
これは、恩田医師が患者さんの父親に「標準治療」について説明した場面を振り返ると非常によくわかります。
患者さんの捉え方は医師とは異なる

恩田医師は、抗がん剤を用いた標準治療がベストな選択肢であることを伝えるために、父親にあるデータを示します。
それは、標準治療を行った患者さんと、民間療法(補完代替療法)のみを行った患者さんの生存率を比較したものでした。
5年後の生存率は、標準治療群は80%であったのに対し代替療法群は50%、という実在するデータです(1)。
父親はきっと、
「標準治療はこんなに生存率が高いのか。だったら標準治療を選びたい」
と思うだろう、と恩田医師は考えたのです。
ところが、父親はかえって憤慨し、こう答えました。
「医者は数字が大事かもしれない。でも確率なんかじゃないんだ。こっちはたった一つの娘の命が守れるかどうか、それを考えてるんだよ!」
がん患者さんが最も知りたいのは統計的なデータではなく、
「自分に効くか効かないか」
「自分のがんが治るか治らないか」
だからです。
このように、がん治療においては、
「現在最良のがん治療が目指しているゴール」
がどこにあるのかを、患者さんと十分に共有できていないケースがよくあります。
「がんが消える」といった「現在最高の医療レベルを持ってしても不可能なゴール」を設定してしまう患者さんとの間で、すれ違いが生じないよう丁寧に理解を共有せねばなりません。
ドラマのラストでクリニック摘発のニュースを見て、別のがん患者である高坂民代(高畑淳子)は医師らにこう言います。
「なんでこんなもんに患者が騙されるか、不思議でしょう?治りたいからよ。生きたいからよ。なんだっていいからすがりたくなるのよ」
こうした患者さんの期待や希望を理解し受け入れつつ、現時点で医療が到達している最高地点を慎重に丁寧に伝えることが、医療者には求められるのだと思います。
また、ドラマ中で腫瘍内科部長の阿久津医師(木下ほうか)は、
「全ての民間療法を否定できないし、するべきではない」
とも語っています。
恩田医師が作成した資料にもあったように、がん患者さんの45%が代替療法を利用しており、その61%は主治医に相談していません(2)。
医師がこうした治療を全否定することは、かえって患者さんにいい医療を提供する妨げになります。
代替療法の中にも、高額ではなく、患者さんのQOLを向上させて治療意欲を高めるものもあるでしょう。
患者さんが上手に医療を利用できるよう、手助けするのが私たち医師の役目だと私は考えています。
以下の記事もご参照ください。
標準治療に関しては以下の記事もお読みください。
(参考文献)
(1) JNCI 110(1), 121–124, 2018
(2) がんの補完代替療法クリニカルエビデンス 2016年版/日本緩和医療学会