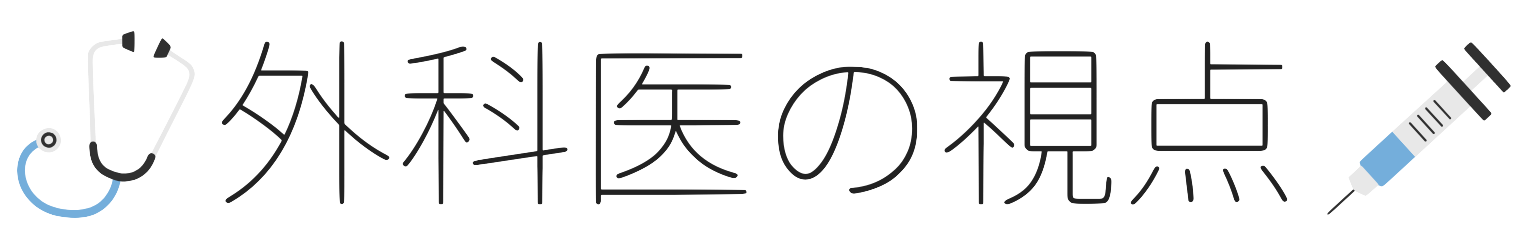東京医大が2010年頃から、入学試験の成績において女子受験生が不利になるよう操作していた事実が発覚し、波紋を呼んでいます。
関係者は、
「女性は大学卒業後に出産や子育てで現場を離れるケースが多く、医師不足を防ぐためだった」
と説明しています。
同じ受験料を課しながら事前に説明なく女性に不利な仕組みが許容され、公然と女性差別が行われてきたことは、にわかに信じられません。
医師を目指して受験勉強をしてきた女子受験生たちの努力を踏みにじる行為とも言えるでしょう。
では、大学当局はなぜ女性医師数を制限する必要があったのでしょうか?
「医師不足を防ぐため」というシンプルな理由だけで納得できるでしょうか?
その正確な理由は当事者らにしか分かりませんが、今回、現場経験をもとに推測してみたいと思います。
あくまで自分の経験に基づく私見ですので、ご興味がある方のみお読みください。
主治医が最後まで診るという呪縛
患者さんを一度担当すれば、最後までその医師が責任をもって診るべきだ、という発想は我が国の医療現場に根強く残っています。
特に年配の医師は若手の頃からそのように教育されてきたため、こうした信念を容易には変えづらいものです。
これが主治医の使命だと思っているからです。
例えば、夜中に担当患者が急変した、というケースでは、たとえ当直医が常駐していてマンパワー的に十分であっても、主治医が呼び出されます。
急変時の対応は主治医が責任をもって行うべきであり、家族への説明もこれまで診療してきた主治医自身がすべきだ、という発想があるからです。
この日が当直明けだろうと、土日祝日だろうと、関係ありません。
同じ科の当直医がいるならシフト制によって分業する方が合理的ですが、この合理性より「主治医の使命」が優先されます。
実はこれは、患者側の意識にも原因があります。
患者さんの状態が急変し、家族が呼び出された時、そこへ今まで一度も会ったことのない当直医が現れると、患者さんや家族は不信感を示します。
きっと主治医の名を出して「◯◯先生は今日はいないのですか?」と不安げに言うでしょう。
「主治医は当直明けなので来ません」
「主治医は休暇中なので来ません」
こうした説明を受けて不安にならない人の方が多いのではないでしょうか?
「今まで自分を一度も診療したことのない医師が、今日に限って自分を(あるいは家族を)診る」
この状況をすんなり受け入れられるでしょうか?
「主治医の先生が一番病状を分かってくれているはずだ」と思う方は多いはずです。
万が一ここで患者さんに一度も会ったことのない当直医が対応し、患者さんに何か問題が起きればどうでしょうか?
「自分のことを分かってくれている主治医だったらこんなことは起こらなかったのではないか?」
と思うかもしれません。
こうした発想があるがゆえに、原則主治医が対応すべきだ、という考えが古くからあるわけです。
患者さんが亡くなった時もそうです。
どんな夜中でも休みの日でも、主治医がお見送りに向かうのが一般的です。
ご遺族の前に最後まで主治医が姿を見せないのはあり得ない。
こういう発想は根強くあります。
よって、現在の医療現場では、患者さんを担当する以上は24時間365日いつ呼び出されるか分からない、という状況を医師は常に受け入れています。
(むろん病院や科によっては職場環境の改善によってこうした古い考え方を払拭できているところもあると思いますが)
女性医師が妊娠・出産する際は、当然ながら作業量に多少の制限を設けなくてはなりません。
妊娠中に、他の医師と同様に夜間に頻繁に呼び出され、当直などの激務を繰り返すのは、母子の健康面を考えても避けねばなりません。
また出産の前後は、やむを得ず一時的に職場を離れざるを得ません。
ここで上述した考えの持ち主は、「最後まで主治医の使命を果たせないなら医師は務まらない」と考えます。
そして「女性医師より男性医師の方がいい」という発想に飛躍するわけです。
本来なら、ここで考えるべきは「女性医師を減らすこと」ではないはずです。
そもそも、こうした激務で現場が疲弊するのは男女共通の問題です。
妊娠中の女性が働きやすいよう職場環境の改善に尽力すべきであるだけでなく、主治医が担当患者を独占的に診るもの、という発想をなくす必要があると思います。
こうした凝り固まったルールで、男性、女性ともに現場は疲弊し、とうに限界を迎えています。
医師と違って看護師は、完全なシフト制によってこれを実現できています。
患者さんの状態がたとえ不安定でも、きっちり定時に申し送りをして担当看護師は変わります。
これに対して、
「いつも見てくれる看護師さんじゃないと不安だ」
と異論を唱える患者さんはほとんどいません。
医師がこうした職場を実現するには、シフト制によってチーム全体で患者さんを毎日診療し、患者さん側には、全医師が病状を把握しているので、毎日診る医師が変わる可能性があるのは普通である、という状況をご納得いただくのが良いと思います。
ただし、こうしたシフト制を行ってもなお、回らない現場は少なからず存在します。
広告
物理的にマンパワーが足りない
科によっては、女性医師が妊娠中に時短勤務となったり、出産のために抜けたりすると、そのカバーがマンパワー的に大変、という部署もあるでしょう。
週に何度も当直し、当直明けもそのまま勤務し、完全な休みは年中通してほとんどなく、ギリギリの人数で回している。
こうした現場はいくらでもあります。
ここで一人でも抜けると、そのダメージは多大です。
突然人が抜けられると困るので、女性医師に対して公然と、
「妊娠するなら事前に言ってくれ。他に人を雇うから」
と恥ずかしげもなく言う人すらいます。
人数的に余裕のない科では、途中で抜けるリスクの少ない男性医師を揃えた方が安全、という発想に至り、女性医師数を抑制したいと思う人が現れます。
当たり前のことですが、妊娠・出産を契機にマンパワーが減ると困る、という状況下で考えるべきは、「女性医師を減らす」ではなく、「女性医師がいても現場が回る方法を考える」であるべきです。
そもそも妊娠・出産は女性だけのイベントとしても、子育ては男女のどちらかが必ず行わなくてはなりません。
両親ともにハードワークを維持しながら、かつ子育ても行う、という働き方は、今の医療現場ではかなり困難であり、育児休暇もまともに取りづらいわけです。
女性医師を減らして男性だけの職場にしたところで、男性が育児休暇をとれない、あるいは育児休暇を取る男性に対して残った男性が冷たい視線を向ける、というようでは、状況は何も変わりません。
このように医師の絶対数が足りない現場では、前述のシフト制は解決策になりません。
医師にしかできない仕事以外は、全て他職種ができるようにする、といった、医師以外との分業が必要になるでしょう。
今こそ、医師の働き方を抜本的に考え直す時です。
現場の意見を吸い上げ、働きやすい環境を整えることが急務だと思います。