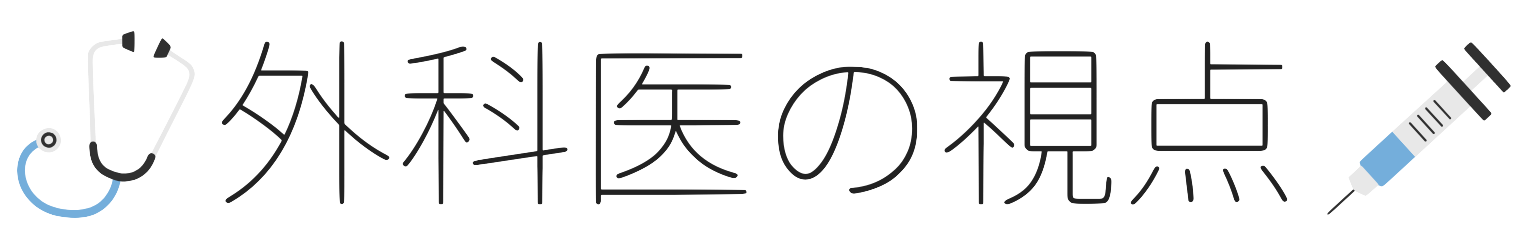藍沢(山下智久)の母親はなぜ亡くなったのか?
知ろうとする藍沢に、死因が自殺だったことをほのめかす手紙を父親はついに藍沢に手渡す。
強い口調で循環器内科に進むよう指示する父に反抗していた白石(新垣結衣)。
だが父はステージ4の肺癌であり、先が長くないために白石を同じ循環器内科医にしたいと考えていたことを、ついに白石は知ることになる。
そして緋山(戸田恵梨香)は・・・
たとえ知ることが不幸につながるとしても、隠された真実を人は暴きたいと思うもの。
第6話のテーマは「秘密」。
というわけで、家族間で秘密にされていた真実を知った藍沢と白石のエピソードを織り交ぜつつ、今回は末期の肝臓癌であることを息子に隠して耐えていた女性がメインに描かれる。
さらに、緋山が良かれと思ってした行為が訴訟の原因になってしまう展開。
まず、肝硬変、肝細胞癌、吐血から死亡という一連の病状が非常にありふれたものであることを、今回のケースを元に解説する。
そして緋山の行為がなぜ危険なのか、ということについて次に解説しよう。
食道静脈瘤はなぜ起こるのか?
突然吐血して倒れた女性がいるとの連絡が入り、ドクターヘリで現場に向かう藍沢と三井(りょう)。
どうやら末期の肝硬変と肝臓癌があり、それによる食道静脈瘤の破裂が吐血の原因であった。
初療室で藍沢が緊急内視鏡を行なって止血し、ことなきを得るが、その後も再出血。
末期の肝硬変に対して治療の手立てがない厳しい状況にもかかわらず、女性は息子に自分の病状を胃潰瘍と偽っていた。
藍沢は現状を正直に息子に伝えるべきだと判断し、肝硬変と肝臓癌で余命が2ヶ月程度であることを息子に知らせる。
だが息子は母親の死期が近いことをすでに悟っており、真実を隠しておきたい母への思いから気づかないふりをしていたのだった。
食道静脈瘤破裂は、救急の現場でよく遭遇する比較的頻度の高い内科救急疾患である。
しかし外傷など外科救急が描かれることの多いコードブルーでは今回が初登場。
なぜ肝硬変で食道静脈瘤になるのか?
食道静脈瘤はなぜ死亡の危険があるのか?
疑問に思った方も多いかもしれない。
まず、肝細胞癌の90%近くがC型肝炎かB型肝炎による慢性肝炎、肝硬変が原因である。
ウイルス性肝炎に長期間冒された肝臓が、徐々に固く変化し、機能が落ちていくのが肝硬変だ。
このほぼ「焼け野原」の状態となった肝臓に肝細胞癌が現れるのである。
よって多くの肝細胞癌患者は、同時に重度の肝硬変を伴っていることが多い。
今回出てきた女性もそうである。
そして重度の肝硬変の3大死因は、
肝細胞癌
肝不全
食道静脈瘤破裂
である。
藍沢と白石が息子に説明していたように、今回の女性はこの3つのいずれでも亡くなる可能性があり、予後が極めて厳しい状況にある。
さて、この中であまり見慣れないのが「食道静脈瘤破裂」だろう。
肝硬変によって食道静脈瘤ができる仕組みは、実は全く難しくはない。
食道、胃、小腸、大腸などあらゆる消化器系臓器で栄養を吸収した血液は、その後全て肝臓に集まる仕組みになっている。
心臓に戻る前に、肝臓で解毒などの作用を受ける必要があるからだ。
いわば、肝臓は関所のようなものである。
この肝臓に向かう太い静脈を「門脈」と呼ぶ。
ところが、肝臓が固く変化する肝硬変になると、その関所を血液が通り抜けにくくなるため、門脈の手前で血流が渋滞することになる。
そして手前の静脈がどんどん太く拡張し、蛇行してできるのが静脈瘤である。
肝臓に近い胃や食道に静脈瘤ができやすいため、肝硬変患者には食道静脈瘤や胃静脈瘤を合併することが非常に多い。
普段は無症状だが、静脈瘤は壁が薄いため、ふとした瞬間に突然破裂するリスクがある。
もともと肝臓の手前で渋滞して圧が高まった血液であるため、破裂すると大量に出血することになる。
それだけで数分で命を落とすこともある危険な疾患である。
今回のこの女性に対する治療中の会話を振り返ってみよう。
吐血した女性に対して藍沢が口から内視鏡を入れて食道を観察。
白石が、
「バソプレシン準備して。輸血まだ?」
と指示。
バソプレシンは血管を収縮させる働きのある薬剤だ。
これによって食道や胃を含む腸管へ向かう動脈血流を減らし、ひいては肝臓に流れ込む血液を減らす治療である。
これによって門脈の圧を下げ、出血を減らすことができる。
さらに藍沢が、
「EVLかけます」
と言う。
EVLとは、「内視鏡的静脈瘤結紮術」のこと。
静脈瘤に輪ゴムのようなループをかけて結んでしまい、止血する方法である。
このほか、静脈瘤内に静脈を固める作用をもつ薬を注入するEIS(内視鏡的硬化薬注入療法)という治療もある。
だがいずれにしても、門脈の手前の静脈は広い範囲で静脈瘤を作っている。
出血している箇所を潰したところで、いつ他のどこかから出血するかわからない。
この女性もこの後すぐに再出血する。
一度静脈瘤を作ってしまうと、これを完全に治してしまうことは不可能だということだ。
よって、肝硬変、あるいはその一歩手前の慢性肝炎の人は、これ以上肝臓の状態が悪化しないようきっちり治療することが大切である。
この女性はステージ4の肝臓癌と診断されてもなお、通院を自己中断していた人である。
おそらく肝硬変で体の状態が悪くなっても不摂生を続けていたのだろう。
なお、EVLまでできてしまう救急医は普通はいない。
基本的には、食道静脈瘤破裂の疑いがあるという情報が入った時点ですぐに消化器内科に連絡である。
今回は消化器内科医から「救急で面倒見てくれ」という無責任な連絡が入ったとの設定だった。
これは確かに「あるある」な展開で、相変わらず救急部目線でのリアルな現場描写に驚くのだが、実際にはこのまま許されることはない。
おそらく救急部部長経由で消化器内科部長に連絡が入り、消化器内科部長から、
「お前か断ったのは!ええ加減にせんかい!」
と、若手消化器内科医(たぶん)が「ブチギレられる」という展開が容易に予想可能である。
広告
緋山の行為は間違いだったのか?
一方緋山はICUで多発外傷の少年を担当していた。
検査の結果すでに脳死であり、回復の見込みはない。
緋山は少年の母親にDNR(「延命処置を希望しない」という意味)について説明をする必要があった。
DNRに母親が同意することはすなわち、心臓が止まっても心臓マッサージを行わない、昇圧剤(血圧を上げる薬)を使用しない、ということを意味する。
緋山はDNRの同意書を用意して母親のところまで行くも踏ん切りがつかない。
結局DNRという形の上での同意より、少年の病状を丁寧に説明し、母親に寄り添うことが大切と感じた緋山は、同意書の取得を諦める。
結果として、なかなか現実を受け入れられなかった母親は、ようやく少年の脳死という状況を理解。
母親からの「息子を抱きしめたい」という希望を聞き、緋山は人工呼吸器を外し、その希望を受け入れる。
ところが、緋山のこの行為がのちに大きな波紋を呼ぶことになる。
この行為が訴訟の原因となっていく様子はこれ以後の放送でたっぷり描かれるが、今回少し説明しておこう。
今回緋山は、DNRの同意を母親からもらうことなく、独断で人工呼吸器を外してしまった。
ではDNRの同意が書面で得られていれば、緋山は訴訟を免れたのか?
というと実はそうではない。
DNRの同意が得られても、原則として人工呼吸器を医師が外すことはない。
人工呼吸は延命処置の一つだから延命処置を希望しない人には人工呼吸器を外しても良いのでは?
と思った方がいるかもしれない。
実は一般的にここで言う「延命処置」は、
「人工呼吸をしていない人に対して人工呼吸を始める」
ということを意味する。
「人工呼吸をしている人に対して人工呼吸をやめる(すなわち患者さんに積極的に死をもたらす)」ことを正当化するものではないということだ。
これまで末期患者の人工呼吸器を外した医師が、殺人容疑で書類送検された事例は複数ある。
だが、たとえば末期の患者さんに対して、
「一度人工呼吸器を外してみて自発呼吸にチャレンジし、次に自発呼吸が危うくなった時には気管挿管しない」
ということを、家族に説明の上で行うのは可能だ。
結局は解釈の問題なので、きっちりルール化することは不可能である。
「患者さんの家族が事態をどう解釈するか」次第ということだ。
今回の緋山のケースでも、母親は緋山を信頼していたし、訴訟を起こす気など毛頭なかったはず。
緋山がほとんど家にも帰らず付きっ切りで少年の治療に全力を尽くしていることを母親は知っていたし、日頃から病状について十分な説明を受けていたはずだからだ。
だが、こういう時によく問題となるのが、これまで病院に姿を見せなかった別の親族からのクレームである。
私は困難な決断を迫られるケースでは必ず、
「他に一緒に話を聞きたいご家族の方はいらっしゃいませんか?必ず全員で納得して治療を受けてください」
と、くどいくらい言うのが癖になっている。
こういうデリケートなケースでは特に、関係する家族の方全員に十分な理解を得た上で医療行為を行う必要があるからだ。
だが、そもそも病院に一度も現れず話したこともない親族は、その存在すら確認できていないことが多い。
よって親族全員に同じように説明し、同じように信頼されることはほぼ不可能だ。
こうして現場の事情を肌に触れて知らない親族の一員が、状況を表面的に見て医療過誤と解釈してしまうケースはよくあるのである。
今回も「母親の兄」という、おそらく病院にこれまで一度も来たことのない人からの訴訟が描かれたのは、まさに「よくあるケース」と製作者らが認識しているからだ。
これを見た医師は誰もが同じように「ありがちな危ない事例」と感じるはずである。
したがって現代の医療現場では、少なくとも書面に残る形での説明が最低限必要、との観点から過剰なほど書類が増えている。
本当に担当医を信頼している人にとっては、サインする手間だけが増えることになっている。
残念ながら、
「目に見える形で書面が証拠として残っているかどうか」
が重要になるからである。
第7話の解説はこちら!