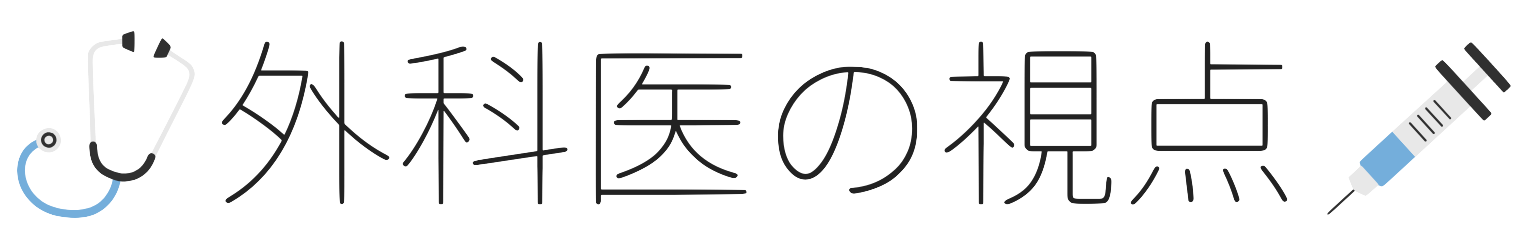医師の仕事は、病気や怪我で苦しむ患者さんを助けることだけではない。
私がこのことを強く感じたのは、医師になって2年目の時だった。
ある夏の日、救命センターに1件の搬送依頼があった。
4歳の女の子が交通事故に遭い、心肺停止だという。
お母さんと手をつないで横断歩道を渡っている最中、曲がって来たトラックに女の子だけが轢かれた。
救急車が現場に到着した時点で、すでに心肺停止だった。
交通外傷で心肺停止状態が長いケースでの救命率は、非常に低い。
救命センターには暗雲が立ち込めた。
搬送されて来た少女は、救命士によって懸命に心臓マッサージをされていた。
黄色いワンピースを着た小さな体が、心臓マッサージのたびに大きく揺れた。
私たちは急いで検査や処置を進めたが、心拍が再開する兆しは全くなかった。
救命は絶望的だ。
部屋の外で待つお母さんに、そのことを伝えねばならない。
こうした場面での家族への説明は、豊富な経験を積んだ医師でないと難しい。
娘の命が突然失われたことなど、容易に受け入れられるはずがない。
その場で泣き崩れるかもしれない。
医師にすがりつき、あるいは「なぜ助けてくれないのか」と大声で罵倒するかもしれない。
まだ経験の浅かった私は、そんなことを考えていた。
ところが、予想もしないことが起こった。
お母さんは自ら初療室に入ってきて、落ち着いた様子でベッドまで歩いて行き、表情を変えず娘の手を握って、
「こら!お姫様になるって約束したよね!」
と言ったのである。
まるで、いたずらをする子供を叱るかのように。
娘の命が失われつつあることなど、想像すらしていないように。
私は深い絶望に襲われた。
少女を救えなかったからではない。
お母さんを、この先、誰が、どのようにして救うのか。
その答えが自分にはなかったからである。
いや、私だけではない。
その場にいた全ての医師がそう思ったはずだ。
知識を蓄え、技術を磨き、必死で努力してきたのに、目の前で大切な命を失った女性を、深い悲しみから救うことができない-。
私がこの時学んだことは、今でも生きている。
病気や怪我で苦しむ患者さんを目の前にした時、私たちが手を差し伸べるべきは本人だけではない、ということだ。
患者さんの家族は、時に本人よりも辛い日々を送る。
患者さんには、毎日懸命にその人を支え、一緒に病気や怪我と闘い、苦痛を共にする家族がいる。
もし本人が亡くなることがあれば、残された家族はその後、その人がいない人生を歩んでいく。
こうした方々にも心を配り、手を尽くす。
そうした態度が医師には必要とされる。
そして多くの診療科では、患者さんの治療に長く携わる中で、たいていこうした関わり方のできる「時間的余裕」がある。
患者さんによって、家族間の人間関係や家庭環境は違う。
医師に求められる適切な関わり方も違う。
こうした能力を身につけるのは容易ではない。
一人一人の患者さん、その家族と近い距離で関わり続けることで、わずかに一歩ずつ、私たちは成長できるのである。
※本記事は医師の守秘義務を鑑み、一部を事実から改変しています。