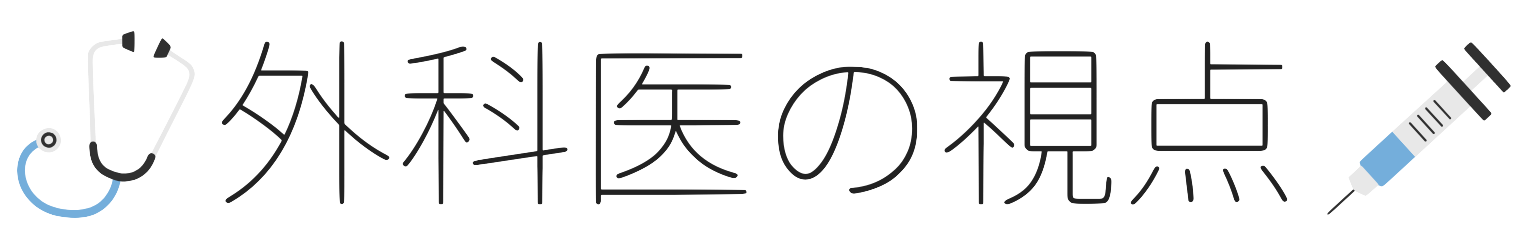我々医師は、ありがたいことに患者さんからお礼の手紙をいただくことが多い。
私は研修医の頃からその全てをファイルに大切にしまっていて、時々見返している。
便箋何枚もに渡る長文をいただくこともあれば、旅行先から絵葉書を送ってくれる人もいる。
その中で、小さな細長い便箋に、細いボールペン字で「手術ありがとうございました」と一言だけ書かれてある手紙がある。
私の忘れられない出会いである。
その手紙の主は、私が胃癌の手術を担当した高齢の男性であった。
真面目で落ち着いた物腰の方で、あまり感情を表に出さない寡黙な方だった。
癌はかなり進行していたが、胃を切除する手術をすることで、病巣をなんとか取り切ることができた。
高齢のため体力回復に時間がかかり、入院が少し長引いたのだが、辛い表情一つ見せず気丈に振舞っていた。
むしろ私の方が心配されていて、病室を訪問するたびに「先生疲れていませんか?」と気遣ってくれた。
ある日、手術が終わったあと病室を覗くと、彼は、
「お疲れでしょう。これで元気をつけてくださいよ。」
と言って、コンビニの袋に入ったコーヒー牛乳とヨーグルトを私に手渡した。
自分のために買った物のようだったので固辞したが、彼はどうしても譲らず、根負けしていただいてしまった。
その後無事退院し、彼は私の外来に通うことになった。
しかしその半年後、肝臓に腫瘍が見つかった。
胃癌の再発だった。
抗がん剤を始めたが、高齢であったこともあり、標準的な量では副作用が強く出た。
点滴をした日は食欲がなく、外を出歩くことが難しいとの訴えがあったので、量を少なくして再開することを提案した。
しかし彼は頑なに断った。
「毎朝、近くの喫茶店に行ってコーヒーを一杯飲みながら、近所の人とおしゃべりをするのが何よりの楽しみで、それができなくなるくらいなら治療はしたくない」
と言うのだった。
私はそれを聞いて、治療をしないのも一つの選択だと思った。
彼の希望するように、積極的な治療はせず、緩和治療を行いながら自然な形で癌と付き合うことにした。
彼は月に1回、奥さんと二人で私の外来に通った。
毎回、
「先生の顔を見ると安心します。楽しくやっています。」
と元気な顔を見せてくれたが、徐々に体重は減り、体力は落ちてきているようだった。
3ヶ月ほどたったある日、私に辞令が出た。
年度末に別の病院へ転勤することが決まったのだ。
患者さんたちに外来でそのことを伝えると、非常に驚かれ、残念がってくれる方が多くてありがたかった。
だが彼は、異動を伝えると驚いた様子もなく、
「栄転ですね。応援しています。」
と一言だけ言ってくれた。
彼の病気は徐々に進行していたが、日常生活に支障が出るほどではなかった。
私は彼に、
「どこかで必ず、急に体調が落ち、今の病気で寿命を迎える日が来る。その準備を今のうちにしておきましょう。」
と言って、在宅医療の準備を整えた。
彼は落ち込んだ様子もなく、常に前向きだった。
そして最後の日、彼はいつものように落ち着いた様子で診察室に現れた。
しばらく雑談したのち、「では、これで」と私が話を切り上げようとしたとき、
彼が「寂しくなります」と一言だけ言った。
私が、
「いい先生が代わりに来ますから、大丈夫ですよ。」
と勇気づけると、彼は、
「先生じゃないと意味がない。」
と言って、突然目の前で泣き崩れた。
私は予想もしないことだったので、何と声をかければ良いか分からず、「大丈夫」と一言だけ言ったことしか覚えていない。
隣にいた奥さんが慌てたように、
「あなた、何してるの!ほんと、すみません、すみません。」
と言って彼を部屋の外に連れ出してしまった。
寡黙であまり感情を表に出さない人だったが、私のことを信頼してくれていたのだと、そのとき知った。
医師はたくさんの患者を相手に診療していて、それぞれが、たくさんの患者の中の一人だ。
だが患者にとって主治医は一人。
主治医にしか相談できない悩みや、吐露できない感情を持っているものだ。
その信頼に応え続けるのが我々医師の役目なのだ、とそのとき強く思ったのだった。
彼の、細く、だがしっかりしたボールペン字の手紙を見ると、そのことをいつも強く思うのである。
※本記事は、ご家族の許可を得た上で一部改変して書いています。
 医学生のときの思い出。私が外科医を目指したわけ
医学生のときの思い出。私が外科医を目指したわけ