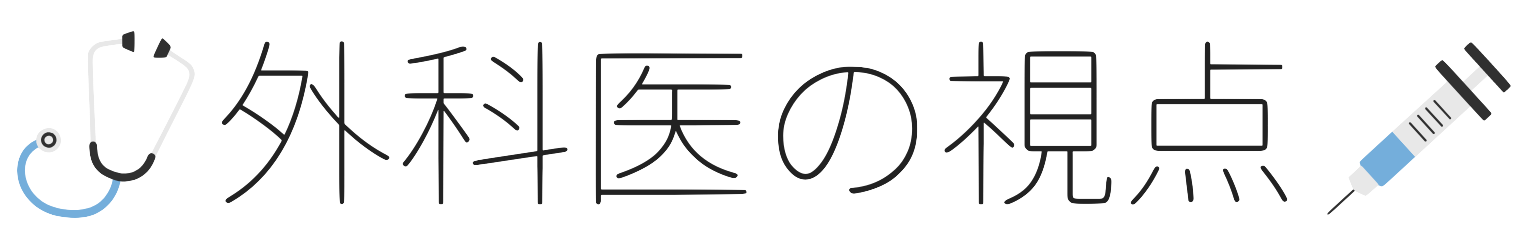コードブルーが他の医療ドラマと違うのは、医療行為や医療者同士のやりとりが、医師の立場から見ても非常にリアルであることだ。
今回も、冒頭から公園で意識を失って倒れている男性を現場で診察した白石(新垣結衣)が、
「Afがある、脳梗塞かも」
と藍沢(山下智久)に連絡する。
藍沢は「MRIの準備をしておく」と応対。
結局この男性は薬物中毒だとすぐにわかるので、このやりとり自体は何の伏線でもないし、ドラマ上はなくても良いやりとりだ。
ほとんどの視聴者には記憶にも残らないセリフだったと思う。
だが、私は毎回こういう「細かすぎて伝わらないモノマネ」のような一見無駄なリアリティに、「やはりコードブルーは違う」と思わされる。
ちなみに、Af(エーエフ)とは、「atrial fibrillation=心房細動」の略で、心臓の「心房」と呼ばれる部屋が細かく震えるような不整脈である。
この不整脈があると、心房内に血栓ができやすくなり、血栓が飛んで脳梗塞を起こすリスクがある。
意識障害の原因として、白石は頻度的に真っ先にこれを考えたというわけだ。
まして心房細動が原因となる脳梗塞は時間が勝負(4.5時間を超えると治療が難しくなる)。
MRIを即座に準備した藍沢の動きも「文句なし」である。
さて今回は、シアン中毒と、外傷手術におけるダメージコントロールの二本立てであった。
もしかしたらダメージコントロールには、「途中で手術中断?そんなことあるの!?」と思った方がいるかもしれない。
しかし私たち外科医にとっては、外傷手術においてよく行う処置である。
今回はこれらについて解説してみたいと思う。
シアン中毒
救急外来では、自殺目的での薬物中毒の受診が非常に多い。
今回は研究一筋だった男性が、ライバル企業に先を越されて成果を上げられず、我が身を憂えてシアン化合物によって自殺を図ったというケースだった。
シアン中毒は、毒物を吸収したあと数秒で吐き気や息苦しさ、けいれん、意識障害などの症状が現れ、数分で死亡するという恐ろしい病気である。
シアン化水素の臭いを私は嗅いだことはないが、「アーモンド臭」と呼ばれる甘いにおいが特徴的とされている。
今回出てきた「甘いにおい」とはこのことである。
中毒は、シアン化水素を含む気体を吸入して起こるケースが多いが、皮膚からも吸収されるため、マスクだけでは中毒を防ぐことができない。
したがって、藍沢らスタッフはマスクに加えてガウンで全身防護、手袋着用と完全防備でヘリを迎えていた。
ここは非常にリアルである。
というのも、このドラマのメインキャラの医師らは不自然なほどマスクをすることが少ない。
とくに藍沢は、屋外での穿頭ドレナージ(頭蓋骨に穴を空けて溜まった血液を逃がす)の際も、気管挿管も、そして途中で手術に手伝いに入る場面ですら、基本的にマスクもしなければ帽子もかぶらない。
患者さんへの感染のリスクと、自身の感染防護の両面から、常にマスクは着用し、清潔が求められる場合は帽子も着用、というのが救急現場では普通である。
もちろんイケメンの藍沢がフルフェイスで防護して表情がわからなくなってはドラマの魅力が損なわれる、という配慮であろう。
ダメージコントロール
重症外傷で手術を行わなくてはならない時、外科医にとっては大きなジレンマがある。
すでに大きな外傷を負っている患者さんのお腹を切り開くことは、さらにもう一つの大きな外傷を患者さんの体に加えることになるからだ。
今回白石が若手フェローの灰谷(成田凌)にダメージコントロールのポイントを問う場面があった。
灰谷は、アシドーシス(血液のバランスが酸性に傾く)、低体温、凝固障害の3つを挙げる。
これらは外傷における「死の3徴」と言われ、この3つがそろうと死亡リスクがきわめて高くなる。
重症外傷での長時間にわたる手術は、この3つをそろえてしまう「とどめの一発」になってしまう可能性がある。
そこで、1回目の手術は短時間の応急処置にとどめ、まず救命を優先する、という段階を踏むことが多い。
これを「ダメージコントロール手術」と呼ぶ。
もともとは、損傷を負った軍艦を最寄りの港に一時的に避難させ、応急処置を行うという軍事用語からきた言葉である。
藍沢の「ダメージコントロールだ」という指示に対し、若手スタッフらが「え?」というリアクションをしていたが、それはこちらとしても「え?」である。
外傷外科ではよく行う手術で、今回ばかりは「藍沢が凄まじいアイデアを繰り出した」のではないからだ。
また、2回目の手術で無事止血できていることを確認した藍沢が、
「腸管損傷を修復しよう」
と言う。
これはつまり、腸が破れていようと、破裂していようと、1回目の手術では「無視を決め込んだ」ということだ。
短時間であれば腸管損傷でも命にかかわることはないからである。
1回目で完全な修復にこだわると、かえって手術を長引かせ、患者さんの命を危険にさらすことになる。
広告
特に、今回のような大量出血時はきわめてシビアな「凝固障害」が現れる。
凝固障害(ぎょうこしょうがい)とは、致命的に血が固まりにくくなる状態のことだ。
今回のケースを見て、「出血しているところがわかっているなら、縫うなりクリップで止めるなりすればいいじゃん」と思った方がいたかもしれない。
「なぜ血も止めずに手術中断などという危ないことをするのか?」と思った方もいたのではないだろうか。
実は、大量出血に対して外科医ができることはかなり限られている。
ドラマ中でも解説があったように、ある一定の出血量を超えると、凝固因子(ぎょうこいんし)が多量に失われることで重篤な凝固障害が生じるからだ。
血液は、血管の外に出て外界に触れると自然に固まろうとする。
これを「凝固能」という。
皮膚の切り傷から出た血がガーゼの圧迫で止まったり、鼻血をティッシュで押さえていれば自然に止まるのはこのおかげである。
この凝固能には、血液中の凝固因子と呼ばれる様々な物質が関わっている。
ちなみに「血友病」とは、生まれつき重要な凝固因子の異常があり、凝固因子の補充を生涯続けなければ血が止まらない病気である。
さて、大量出血で凝固因子が失われて凝固能が弱まってくると、外科医が出血点をいくら押さえようと、糸と針で縫いこもうと、何をしても血が止まらなくなる。
どこから血が出ているか明らかにわかっているのに手がつけられないのである。
ここが手術の限界である。
ガーゼでパッキングして出血を下火にするにとどめ、一旦手術を中断して輸血と凝固因子の補充、全身状態の立て直しにシフトチェンジするのが良い。
ダメージコントロールでは、お腹を閉じずに開けたままガーゼやフィルムでフタをしてICUで管理する。
一定時間が経過してから再度開腹し、止血を確認するという流れになる。
今回もあったように、再手術では「ガーゼの最後の1枚が臓器に貼り付いて剥がれにくい」ということはよくある。
肝臓に完全にくっついて、剥がすと肝臓の被膜が剥がれて再出血することもよくある。
ただこの場合でも、血液の凝固能が立ち上がっていれば、嘘のように容易に止血が可能である。
まさに、「血を止めるのは外科医ではない、患者さん自身だ」と思わされる瞬間である。
自分の目の前で患者さんの命が失われつつある時、腕に自信のある外科医ほど、「自分の力でなんとか救いたい、救わなければ」と思うものだ。
しかし患者さんにとっての最善が、自慢の腕をふるうことなのか、外科治療の限界を知って一旦手を引いて大局を見ることなのか、常に考えることが大切である。
最後の場面で白石が灰谷に「臆病は医師の資質だ」と語っていた。
おっしゃる通りだ。
むしろ私は、能力の高い外科医こそ「手術」という治療の限界を正確に評価できる「謙虚さ」を持ち合わせるべきだと思っている。
というわけで、現役外科医による「ちょっと為になるうんちく解説」はここまで。
興味を持って読んでいただける方がいらっしゃれば幸いです。
来週もお楽しみに!
コードブルー全話解説記事目次ページへ→コードブルー3 医師による全話あらすじ/感想&解説まとめ(ネタバレ)
第2話の解説はこちら
コードブルー3 第2話感想|医師が思う新人の医者が全然ダメな理由
第4話の解説はこちら
コードブルー3 第4話感想|緊急手術に医師が感じる強烈な違和感
人気のまとめ記事を見たい方はこちらをどうぞ