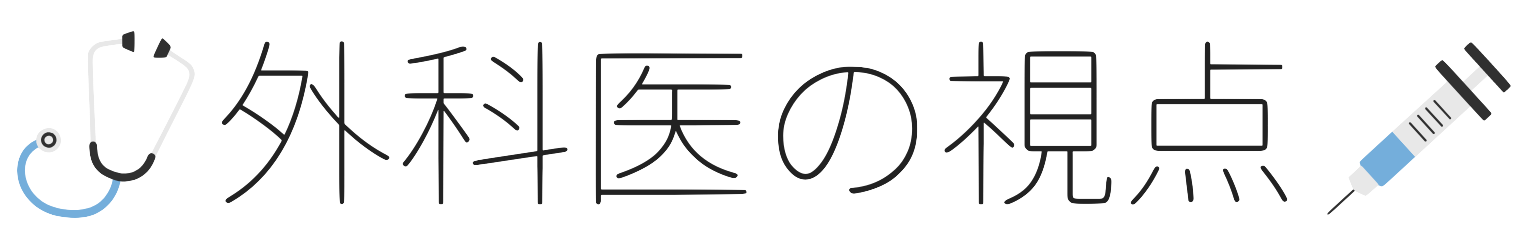2019年版「白い巨塔」が、5夜連続で放送されました。
原作は50年以上前の小説ですが、原作の雰囲気をそのままに、舞台を現代に変えて作られた作品です。
今回の財前五郎(岡田准一)は、「腹腔鏡の名手」であり、かつ「肝胆膵の若き権威」という設定。
原作小説の財前は胃がん手術のスペシャリストで、特に胃の入り口、噴門部の胃がん手術を得意としていました。
当時、この部位の胃がんは診断も手術も難しいとされていたためです。
ところが、技術の進歩により、現在は噴門部の胃がんでも多くの外科医が安全に手術できるようになっています。
また、胃がんに対する腹腔鏡手術は広く普及しており、財前を「新しい技術で世界的に名を知られた外科医」とするには、原作の設定のままでは無理がありました。
一方、肝胆膵領域、特に膵がんの腹腔鏡手術となると話は別で、ごく一部の慣れたスタッフが揃った病院でしか行われていません。
ドラマ中でも、
「一般的に膵臓がんへの腹腔鏡手術は推奨されていない」
というセリフがありましたね。
多くの施設は、腹腔鏡ではなく従来の開腹手術を行っているためです。
財前を、まだ技術が安全に普及しているとは言い難い分野のパイオニア、としたところに、秀逸な工夫を感じました。
さて、「ドクターX」のようなコメディとは異なり、「白い巨塔」のような硬派なドラマを作るには、医学的なリアリティとエンタメの両立を目指すのが非常に大変だと思います。
視聴者も、これほどリアルさを演出したドラマであれば、
「これはリアルなのかフィクションなのか?」
と疑問に思うシーンは多いでしょう。
中でも今回の記事では、財前の訴訟に関して注意すべきポイントとして、
・術前にPET撮影をしていれば解決した、という問題ではない
・術後に執刀医が診察していれば良かった、という単純な話ではない
という2点について解説したいと思います。
財前は医療ミスをしたのか?

財前は、膵頭十二指腸切除の術後に亡くなった患者さんの遺族から訴訟を起こされます。
術後の病理解剖で、血管内リンパ腫による肝不全が死因であったことが判明し、これを術前あるいは術後早期に見つけて治療介入しなかったことが問題視されたためです。
財前は、教授就任後に一層高慢になり、周囲の意見に耳を傾けず、唯我独尊を貫いていました。
術前に内科の里見(松山ケンイチ)や部下の柳原(満島真之介)からPET検査をするよう進言されたにも関わらず、これを黙殺していたこと、
術後に患者さんを一度も診察せず、異変に素早く対応できなかったこと
が争点になりました。
実際、膵頭十二指腸切除術後に急に高熱が出て状態が悪化することは珍しいことではありません。
その際、まず考えるべきなのは、頻度の高い2つの合併症、
「胆管炎」か、「膵液漏(瘻)」
です。
膵液漏(ろう)とは、膵液がお腹の中に漏れること。
胆管炎は、胆管に細菌が入り、感染を起こすことです。
いずれも比較的よくある合併症で、どれほど腕のいい外科医が手術をしても、これをゼロにすることはできません。
財前も即座にこの2つを疑い、そのつもりで対応するよう部下に指示を出していましたね。
一方、今回問題となった血管内リンパ腫は、ドラマ中でもあったように「極めてまれ」な事象で、術前に見抜くことは不可能に近いでしょう。
法廷では、
「PETを撮影していればもっと早く手を打てたはずだ」
とした里見の意見が重視されました。
確かにこれは正しい主張ですが、CTでも分かりにくいような初期の膵がんでは、術前のPET撮影は一般的には必要ではありません。
むしろ、膵がんとは全く関係のない、治療する必要のない所見が発見されてしまうことによって、余分な精密検査が必要となり、かえって治療方針が乱れる恐れがあります。
こうした行為は、スムーズながん治療を妨げる点で、患者さんにとって大きな不利益になります。
「何でも検査すればいい」というものではありません。
患者さんにとって「必要十分」な検査を行うことが大切です。
また今回は、術前に血液検査で肝機能の異常があり、肝転移も疑われていました。
しかし肝転移を疑うのであれば、PETよりMRIを行うのが一般的ですし、そもそもCTでも写らないような微小な肝転移のせいで肝機能異常が起こることは考えにくいものです。
何らかの肝臓の検査が必要とはいえ、全身の遠隔転移検索を目的としたPETが不要だと考えた財前の判断に、医学的に問題があったとは言えません。
以上のことから、財前の行為を医学的に「過誤」だと言うには少し無理がありました。
彼が法廷で語った、
「現代医学の水準を超えるものであり、どうしようもない不可抗力、もしくは不運だった」
というのは、医学的には正論だと言えるわけです。
では、何が問題だったと言うべきでしょうか。
2つのポイントがあります。
「教授不在では機能しないチーム体制」と、「家族や患者からの不信」です。
エースに頼り切ったチームの危険性

術後の対応が遅れた一因は、手術直後に財前がドイツに学会出張に出かけていたことでした。
法廷でも、術後に財前が一度も診察しなかったことが問題視されましたね。
では、「執刀医が毎日診察すること」が理想的な解決策なのでしょうか?
必ずしもとそうとは言えません。
医師は大勢の担当患者さんを抱え、毎日手術や検査を行い、外来業務をこなしています。
学会発表で自分の持つ知見を他の施設に共有することもまた、他の患者さんを救う一助になる、大切な仕事です。
その道のエキスパートであれば、なおさらそれは重要な任務でしょう。
一人の患者さんに一人の医師が常につきっきりで対応せよ、というのは無茶な話ですし、
「術後に問題が起きれば即座に執刀医が病院に来て診察する」
という方針は、患者さんにとってはかえって危険なシステムです。
結果的には、必ず他の患者さんにしわ寄せが生じるからです。
よって、医学的な観点から問題視すべきは、
「教授が不在になると途端に術後管理のクオリティが落ちる」
というトップダウン体制だったと言えます。
本来はチーム医療により、一人の医師に治療方針が全て委ねられることはありません。
複数の医師が同時に患者さんを診て、誰かが異変に気付いて適切に対応すれば、一人の医師が学会出張していようと、他の手術に入っていようと、患者さんに不利益はないはずです。
医療現場では、誰が抜けても同じクオリティの医療が提供できる、というチーム体制を構築しておく必要があります。
むしろ、そのような体制を作れなかった前教授の東(寺尾聡)にも問題がありますし、そのトップダウンを引き継いだ財前がこの仕組みを容認し続けたことにも問題はあったといえるでしょう。
どんな組織にも、コミュニケーションが不得手な人や、「腕は抜群でも性格に難あり」というような人はいるものです。
重要なのは、そうした多様な人材が適材適所に配置され、不得手な部分を互いに補い合うことで、組織としていつも安定したパフォーマンスを発揮できることでしょう。
その点では、医師は常に謙虚に他人の意見を受け入れる事が大切ですし、財前のような傲岸不遜な態度では、大切な情報も耳に入りにくく、かえって自らを危険にさらす、というわけです。
広告
患者さんからの信頼の大切さ

今回の訴訟のもう一つの原因は、患者さんからの不信でしょう。
上述した医学的な事実を踏まえれば、術前の段階で謙虚かつ丁寧に、
「誰が手術をしても予期せぬ事態は起こりうるし、ゼロリスクを求めるなら手術はできない」ということ
「術後に何らかの問題が起きた際には、自分に限らずチームのメンバーが適切に対処する」ということ
を説明しておくべきでした。
「自分なら必ず手術はうまくいく」という傲慢な態度は言語道断。
術後に問題が起きた時にも適切に対処できて初めて「うまくいった」と言えるものです。
手術そのものは、外科治療のほんの入り口に過ぎません。
手術直後に「成功」などと言うことはできないのです。
「手術は成功したって言うたやないですか!」
という患者さんの妻の厳しい言葉は、「手術が成功しなかったこと」に対してではなく、「手術リスクの説明を怠ったこと」に対する批判と捉えるべきでしょう。
また今回のケースに限って言えば、少なくとも財前から、
「私は術後1週間ほど学会出張のために病院を不在にするので診察はできませんが、他のチームメンバーがきっちり診療するので、その点はご安心ください」
という説明は必要でした。
患者さんからの信頼がなければ医療は立ち行きません。
残念ながら、財前は皮肉にも死を目前にした床上でそのことを悟ることになったのでした。
財前は野心に溢れた能力の高い男でしたが、権謀術数に揉まれるうちに次第に自分を見失っていった孤独な人でもありました。
彼は自らの「野心」を自力でコントロールしているつもりだったでしょうが、結局はその野心を利用したいと考える周囲の人間に翻弄された人生だったとも言えます。
財前が亡くなった時、義父の又一(小林薫)が言った、
「無理をさせすぎた」
という言葉は、非常に的確に、財前の「不幸」を言い表していたと思います。
5日間では描ききれない、深い人間描写、群像劇が小説「白い巨塔」の魅力です。
ドラマで興味を持った方はぜひ、原作小説も読んでいただきたいと思います。
こちらもどうぞ!
 医療ドラマでよく見る教授回診は本当にあるのか?
医療ドラマでよく見る教授回診は本当にあるのか?