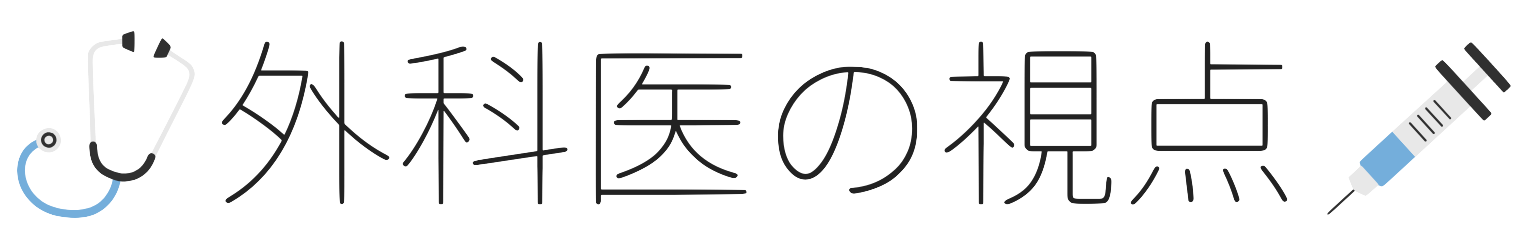昨日(4月6日)の朝日新聞の天声人語は、こんな一節で始まりました。
もしも、こんなアナウンスがあったら・・・。
「機内に急病の方がいます。お客様の中に、お医者様はいらっしゃいますか。ただし男性のお医者さまに限ります」
そんなばかな。
しかし実際、似たようなことが起きた。
相撲の土俵で。
4日、京都であった舞鶴場所で、挨拶中に土俵の上で倒れた市長を救助した女性に、行司が土俵から降りるよう繰り返しアナウンスをしたことが物議をかもしています。
土俵の上は「女人禁制」とはいえ、「人命より伝統を優先するのか?」と批判されているわけです。
私もこのニュースに関して、以下のようなツイートをしました。
お詫びしても、もう手遅れです。
次同じことが起こったら、女性は土俵に上がることを必ずためらいます。
心肺停止は、数秒のためらいが生死を分けるんです。
関係者全員で生涯かけて猛省して下さい。土俵で心臓マッサージしていた女性に「降りて」 京都:朝日新聞デジタル https://t.co/tSgsLt4mx8
— 外科医けいゆう (@keiyou30) April 5, 2018
心肺蘇生(CPR)の重要性については、このブログでも繰り返し述べてきたことです。
ところが今回の天声人語を読み、自分が批判の方向性をやや誤っていたことを自覚しました。
天声人語では、これまで女性官房長官が内閣総理大臣杯を手渡したいと言った時も、女性知事が知事賞の授与に意欲を示した時も、協会は女性が土俵に乗ることを許さなかったことに触れ、
「一方に例外なしで守られてきた伝統があり、一方に緊急事態があった。間に挟まれ動転した行司の心理もわからなくはない」
と書かれてあります。
確かに、その通りです。
今回土俵から降りるようマイクでアナウンスした行司は、
「動揺した、女性が上がっているというのが頭のなかで膨らんだ」
と説明しています。
問題は、人命より伝統を重んじた協会の体質よりむしろ、この事態に対して関係者が「気が動転して適切な対応ができない」という、不適切なリスクマネジメントにあります。
YouTubeで閲覧できるその時の映像を見ると、このことはさらにはっきりと実感できます。
最初に土俵に上がった女性(看護師)が胸骨圧迫(心臓マッサージ)を始めるまで20秒もの間、倒れた市長を取り巻く6、7人の男性は何もしていません。
女性は、何もできない男性陣を押しのけるようにして市長のそばへ向かい、胸骨圧迫を始めているのがわかります。
昨年7月には、新潟県で野球部のマネージャーであった女子生徒が練習直後に倒れて死亡したニュースがありました。
その際私は「野球部女子マネージャー死亡の報道、心室細動の解釈に疑問」という記事で、
「BLS(一次救命処置)は一般人でも身につけておくべきとされるが、学校教員、とくに運動部の顧問はもはや一般人ではない」
と書きました。
プロスポーツの現場にも全く同じことが言えます。
まして、相撲のように肥満した男性が激しい運動を行うような現場では、心血管系のトラブルが起こるリスクはあまりにも高いのです。
当局は「人命に関わる状況で伝統を重んじたこと」よりむしろ、
「目の前で人が倒れた時に何をすべきかを、関係者が誰も知らなかったという衝撃的な事実」
を自省的に振り返るべきです。
一次救命処置とは?
では、目の前で人が倒れた時は何をすれば良いのでしょうか?
私はこのブログでこれまで、この「一次救命処置」についてくどいほどに繰り返し書いてきましたが、今回もう一度書いておきます。
一次救命処置とは「BLS:Basic Life Support」と呼ばれる一連の応急処置のことです。

(日本ACLS協会ホームページより引用)
これは医療関係者以外でも行わなければならない処置だとされています。
なぜなら、救急車が到着するまでに一般人が心肺蘇生を行えば、生存確率が飛躍的に上昇するからです。
中でも重要なのが胸骨圧迫(心臓マッサージ)です。
BLSでは、人工呼吸は「可能であれば」という位置づけです。
判断に自信がなくても、とにかく胸骨圧迫を行うことが大切です。
胸骨圧迫の一つの目的は、止まってしまった心臓を外から繰り返し圧迫することで心臓のポンプ機能を代替することです。
本来自動で動かなくてはならないポンプを、体外からいわば「手動」で動かすことで、通常の30~40%の血液が心臓から拍出できます。
これによって脳への血流がかろうじて保たれます。
脳は酸素不足に対して非常にデリケートな臓器です。
心停止によって脳への酸素供給が途絶えると、3〜5分で脳への障害が始まります。
こうなると、仮に心拍が再開したとしても脳に後遺症が生じ、場合によっては永久に意識が戻らなくなります。
今回の件が本当に心肺停止であったなら、男性たちが何もできなかった20秒は「気の遠くなるほど長すぎる時間」です。
一方で上図で示されるように、同時にAEDを装着し、電気ショックが必要な波形かどうかをAEDに判断させます。
AEDは、ショックの必要がある場合のみ音声で教えてくれるので、仕組みを知らない人でも使える器械です。
上図にあるように、AEDでの解析を2分ごとに繰り返し、ショックが必要な状態になればショック、そうでなければ胸骨圧迫を継続します。
映像を見ると、最初に胸骨圧迫を始めた女性が近くにいる男性に声をかけ、男性が時計を見る姿が映っています。
女性は、今の時刻を把握した上で「2分ごとに声をかけてください」と指示したはずです。
「さすが看護師」と言いたいところですが、これを現場の人間ができるよう普段からトレーニングしておくべきだったと言えるでしょう。
ともかく今回の件は、「伝統と人命」の議論に終始させてはいけません。
あらゆるスポーツの現場の人間が学ぶべき一つの教訓を提示した、と論じるべきでしょう。
こちらの記事もご参照ください。