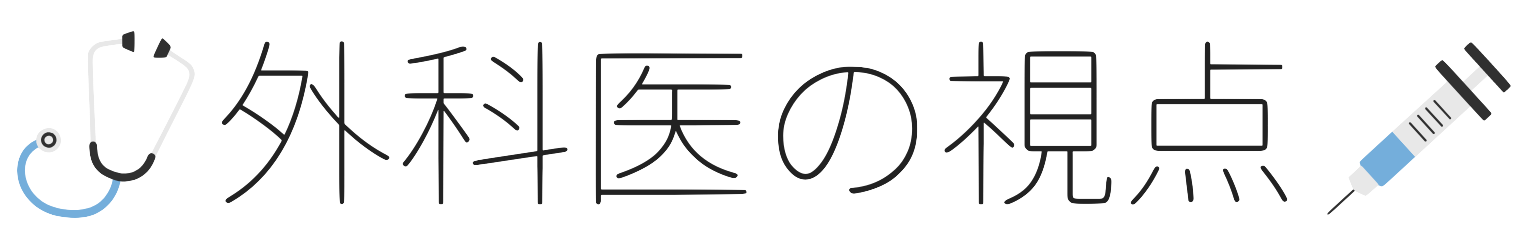期間限定、医学生専用の質問フォームです。
医学的知識やプライベートなことなど、何でもOKです。
ただし、専門外の領域に関する複雑な質問にはお答えできませんのでご容赦ください。
国試に関連するご質問でもOKです。
※返答にはお時間をいただくことがあります。
※全てにはお答えできませんので、他の閲覧者にとって有益と思われるご質問を優先してご紹介していく形にします。
以下フォームをご利用ください。
名前はペンネームでもOK(Twitterされている方はアカウント名でどうぞ!)。
以下、質問に回答していきます。
Q&A
質問者:たまごロールさん
医学科6年です。 初期研修が始まるまでにどのような勉強をしておくのがいいでしょうか。
今のところ、けいゆう先生が記事で勧めていらっしゃった「【分野別24冊!】研修医におすすめの読むべき本/参考書/医学書」の中で気になる本を読んでみたり、私は志望科(消化器外科です)が決まっているのでまずはその科の医学英語を覚えるなどはしておりますが、これで良いのかと不安です。
恐れ入りますが、少しでもアドバイスを頂けると幸いです。
宜しく御願いいたします。 (以前国試に関する質問をさせていただきましたが、非常に参考になり、誠にありがとうございました。)
初期研修が始まる前は、そんなに焦って勉強しなくても大丈夫ですし、勉強してもあまり効率がよくありません。
現場に出ると「何を勉強しなければならないか」が肌に触れて分かりますので、ここで一気に勉強すれば、スポンジが水を吸収するように知識は身につきます。
ただ、ある程度準備をしておくことは悪くありませんので、おっしゃる通り私の記事から書籍を読んでおくのは有効です。
また、医学英語こそ、必要になってからで大丈夫です。
具体的な必要性が見えにくいうちから手をつけても、あまり身につきにくいでしょう。
今年は医学生、研修医向けに書籍が出ますので、ぜひそちらも手にとって読んでみてください。
質問者:メロンパンさん
いつも興味深い記事をありがとうございます。
私は普段の勉強で「病気がみえる」シリーズを使っているのですが、これは研修医になってからも使えるものなのでしょうか?
それともこれでは不十分で、ゆくゆくは買い直すものなのでしょうか?
ありがとうございます。
「病気がみえる」シリーズは学生向けですね。
研修医になってからはほとんど参照することはないと思います。
というのも、臨床に出れば研修医向けに各科の便利な教科書が多数出ていますので、これらを購入することになるからです。
これに関しては、全く心配ご無用です。
多くの人は、卒業時に後輩に譲り渡している気がしますね。
質問者:カルバーさん
先生のツイート、楽しく見させてもらってます!
外科系志望の医学生なのですが、手術の腕は何で決まりますか。
もちろん、手術件数や指導医の方などが重要なのは心得ていますが、器用さなどその人自身の適性や資質などもあると思うのです。 教えて頂けると嬉しいです。
いつも見ていただいているとのこと、ありがとうございます。
「手術の腕」は、おっしゃる通り適切な指導のもとで良い手術をいかに多く経験するか、良い手術をいかに多く見るか、ということがまず大切ですね。
本人の資質としては、腕の良い人の手術をコピーアンドペーストする、という愚直な素直さが必要です。
自分のやり方など二の次。ひたすら手術を見て、動画を見て、それを完全にトレースする、という意欲が大切ですね。
当たり前ですが、素直な人は手術は上手くなります。
一方、抜群に器用である必要はありません(全く不器用、というのでは困りますが)。
手術は鍛錬によって流れを身につけることができますので、器用さという生まれ持った資質を持った人だけしか務まらないものではありません。
この点はご安心ください。
質問者:サルコペニアさん
国試まであと2週間になってしまった受験生です。国試前の気持ちの浮き沈みが激しいです。ひとこといただけると嬉しいです…!!
「ひとこと」ですね。
国試の合格率は例年90%ですから、落ちる確率は10%しかないので安心してください。普通にやっていれば大体の人が受かります。
あと落ちる人はたいていサルコペニアさんのように心配性の人ではなく、余裕をこいている人です。
質問者:だいすけさん
いつも楽しくブログを拝見しています。
いくつか質問があるのですが、 学生はあまり知らないけれど、臨床の場では常識になっているトピックスはありますか?
国家試験終了から、働き始めるまでに最低限これだけはやっておいてほしいという勉強などはありますか?
お答えいただけると幸いです。
いつも見ていただいているとのこと、ありがとうございます。
実は臨床現場に出ると、学生の頃に学ばなかったことばかりが目の前に現れるので、相当面食らうと思います。
現場の「常識」など看護師さんの方がよく知っているので、最初は「今まで自分は一体何を勉強したのか」と落ち込むでしょう。
そこで、このブログでは国試終了後から働き始めるまでに、あるいは働き始めてからすべきことをまとめた記事があります。
ぜひ、読んでみてください。
今回の疑問の答えが書いてあると思います。
生活のことを含めた総論↓
 非公開: 誰も教えてくれない、初期研修医のうちに必ずやるべき7つのこと
非公開: 誰も教えてくれない、初期研修医のうちに必ずやるべき7つのこと
勉強のこと↓
 初期研修医の勉強法|必ず勉強しておくべき5つのこと
初期研修医の勉強法|必ず勉強しておくべき5つのこと
質問者:たまごロールさん
いつも先生のツイート、楽しく拝見しております。
国試1ヶ月前の過ごし方ですが、回数別や今まで使ってきた教材をしっかり繰り返して知識を定着させることが肝要だと思います。
しかし、その一方でもう模試も全て終了したため、初見で問題を解く機会というのはありません。
そこで二、三日に一度程度でも新問に触れる機会を作るべきか、それとも今まで受けた模試の直しなどを通して、やってきたことを確実にしたほうがいいのか、先生のご経験から何かアドバイスが頂けると幸いです。
ありがとうございます。お疲れ様です。
私も性格的に心配性だったので、早めに国試向けの模試や過去問を解き終わり、同じ悩みを抱えていました。
たまごロールさんは、ご質問から察するにかなり真面目に勉強されてきた方だと思いますので、問題の振り返りは、すでに分かりきった問題を何度も再見する点で若干無駄が多いかもしれません。
そこで提案としては二つあります。
一つ目は、新たな問題を解くのが好きな方であれば、内科認定医や総合内科専門医などの問題集を利用する方法です。
実際私の周囲の優秀な人たちは、この方法で最後の1ヶ月、知識固めをしていました(当時は総合内科専門医問題集はなかったので内科認定医のものを使っていました)。
私も問題を解くのは好きな方だったのですが、英語の勉強を同時にしたいという動機からハリソンの問題集を解いていました。
“Harrison’s Principles of Internal Medicine Self-Assessment and Board Review”というものです。
残り1ヶ月なので、この方法なら苦手な部分の強化に特化した方が良いと思います。
二つ目は、苦にならないならレビューブック(あるいはイヤーノート)の振り返りです。
私はレビューブックに緑マーカーをひたすらひいて赤シートで隠して隅々まで覚える、というのをやっていました。
眺めるだけでは知識は定着しないし眠くなるだけなので、こういう頭に負荷をかける方法が理想的だと思います。
しんどい方法ですが、結局丸暗記がモノを言うのでおそらく最も効果は高いです。
あくまで私見ですので、他の方々のご意見も参考にしつつ、ご検討ください。
頑張ってください!
質問者:しゃさん
消化器外科の先生方が糖尿病、高血圧、脂質異常症、心疾患などの並存症を持った患者さんを手術することになった時に内科にコンサルトする条件みたいなものはありますか?
重要なご質問ではありますが、これは施設によって様々なので、一概に回答するのは難しいと思います。
おそらく、科間の取り決めや暗黙のルールによるでしょう。
並存疾患がある方を全例コンサルトするわけにはいかないので、ある程度重症のものを選択的にコンサルトする形になると思います。
私の経験上は、例えば術前に新規で判明した糖尿病や、インスリン使用中の糖尿病は糖尿病内科に併診を依頼することが多いと思います。
心疾患なら、冠動脈疾患の既往があり、2剤以上の抗血小板剤を内服している、などが、一つの目安になるでしょうか。
自信がない状況で自己判断でコンサルトすると、他科の医師から苦情が入るリスクもありますので、やはり事前に上級医に確認が必要でしょう。
質問者:ひとみんさん
けいゆう先生、いつもお世話になっています。バリバリ研修中です。(笑)
消化器科の有名なオペでの使用器具の名称と使い道の覚え方って何かないですか??
めっちゃ困ってます。
器具(ペアン・コッヘル・サテンスキー等々)の例も示していただけたら非常に助かります。
よろしくお願いします。
お疲れ様です。
端的に言うと、「覚え方」は必要ないんです、嫌でも覚えてしまうので笑
ただ研修医の先生だと毎日手術を直接担当するわけではないので、そういうわけにはいきませんよね。
私が研修医の時と比べると、かなりいい教科書が出ているので、こういう入門書を使うのはすごくオススメです。
例えば、以下の本は私もよく知っている先生が書かれたものですが、非常に分かりやすいですよ。
あとは、このブログにもオススメ本をいくつか紹介している記事があるので、ぜひ見てみてください。
 志望科別に解説|外科研修医/専攻医におすすめの本・医学書・手術書 <2020年版>
志望科別に解説|外科研修医/専攻医におすすめの本・医学書・手術書 <2020年版>
広告