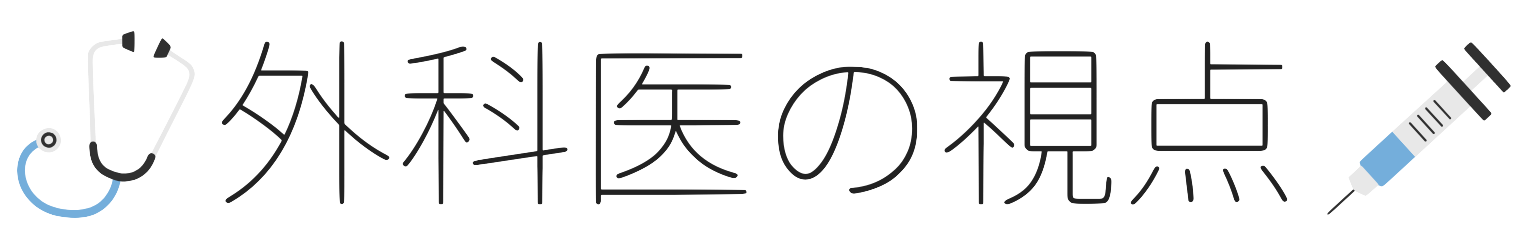ドクターXは、昭和の古くさい時代を舞台に最先端の医療をやる、という、いわゆる「ファンタジーもの」である。
大門が「バイト」として参加する総合外科では、大昔のように、心臓、呼吸器、消化器の疾患を同じ科の医師が担当する。
画像検査の結果はシャーカステンにフィルムを掲げて蛍光灯の光に透かして見るという古臭さ(もちろん今はパソコンの画面で見るのが一般的)。
まさに山崎豊子が小説「白い巨塔」を書いた1960年代をイメージしているようである。
そして今回は、患者の権利は尊重されず、すべての治療方針は医師が決めてしまう、というまさに「古き悪しき」時代の医師と患者の関係が描かれた。
セカンドオピニオンという言葉など存在しなかった時代だが、患者にセカンドオピニオンを希望された猪又(陣内孝則)は、
「患者にとって一番大切なものは医者に対する絶対的な服従」
「セカンドオピニオンなんて言い出す患者は切り捨てろ」
などと言い放つ傲慢さ。
あまりの同業者のダメっぷりに、見ているこちらもドラマであることを忘れて赤面しそうになるほどだ。
言うまでもないと思うが、セカンドオピニオンは近年ではかなり広まっており、医師の側から提案することもある。
多くの病院にはセカンドオピニオン外来が用意され、お金はかかるが(1〜3万円くらい)スムーズに受診できる準備が整っている。
他の医師の意見を聞いてみたい、と思った時は提案しても全く問題ない。
きっちり資料を整えて準備するのが主治医の義務である。
さて今回は、甲状腺オカルト癌というまたしても珍しい病気が登場した。
ドクターXといえば、
「名探偵コナンばりに大門の周囲で必ず人が倒れ、かつその人はいつも珍しい病気」
というのが定番となっている。
おまけに毎回VIPばかりで、いつも入院するのは特別個室である。
医学的な整合性については、若手外科医たちや、海老名(遠藤憲一)、鳥井(段田安則)らがかなり詳しく説明してくれた通り、非常にリアルである。
だが私の目から見れば今回もたっぷり突っ込みたいことがあるので、お時間のある方はお付き合いいただきたい。
今回のあらすじ(ネタバレ)
大門(米倉涼子)は東帝大学付属幼稚園に検診医として派遣されるが、その日偶然にも園長である三鴨(平田満)が倒れてしまう。
大門は三鴨を東帝大病院に搬送。
検査の結果が肺癌であることを三鴨に伝え、切除すべきであると説明するが、なぜか三鴨は煮え切らない。
実はすでにステージIIIAの肺癌と診断されており、手術は不可能として抗がん剤治療を行なっていたが、その主治医が猪又だったからである。
オペは絶対に反対と言い切る猪又は、切除は可能と主張する大門と対立。
しかし術前カンファレンスで院長の蛭間(西田敏行)は手術を行うことを決定し、執刀医に猪又を、第一助手に大門を指名する。
術中に血管損傷を起こすも何とか腫瘍を切除し、手術を終わろうとする猪又に大門は、
「まだオペは終わってないので」
と執刀医を無理やり交代。
何と原発巣は甲状腺癌であること、そして肺の腫瘍は原発性肺癌ではなく甲状腺癌の転移であると説明。
これを見抜けず抗がん剤を続けていた猪又の誤診を非難する。
呆然とする猪又の前で大門は甲状腺腫瘍摘出を行い、無事に根治術を成功させる。
甲状腺オカルト癌とは?
転移巣が先に見つかり、原発巣を検索しても発見されず、その後原発巣として甲状腺に微小な癌が発見されるものを甲状腺オカルト癌と呼ぶ。
実際甲状腺の腫瘍は症状があまり出ないため、検診や他の目的で撮影した画像検査で偶然に見つかることが多い。
そして今回のように、原発巣は1センチ以下と小さいのに、他の臓器に大きな転移巣を形成するケースは実際にある。
しかも今回の甲状腺乳頭癌というタイプは進行がきわめて遅くて予後も良く、術後10年生存率が90%以上とされている。
ゆとり世代の若手外科医たちが説明していた通りである。
余談だが、「オカルト癌」は甲状腺に限らずどの臓器の癌でも用いる用語である。
原発巣を検索しても全く見つからないケースもあり、これを「原発不明がん」と呼ぶ。
こういう癌を治療する指針を示す「原発不明がん診療ガイドライン」があるくらい、まれとは言えない病態である。
だが、そもそも本当に今回のケースは猪又の失態なのだろうか?
私は全くもってそうは思わない。
なぜそう言えるか?
その理由を説明しよう。
広告
猪又を責められない理由とは?
ある腫瘍が原発巣か転移巣かがわからなければ、その組織をとって(生検して)調べるのが普通だ(「病理検査」と呼ぶ)。
今回も腫瘍の組織をきっちり調べてあり、これを見た上で、
肺の腫瘍は転移巣ではなく原発性肺癌である
と診断されている。
画像検査で肺癌として矛盾がなく、病理検査の裏付けまであるとなると、
「肺癌でないことを見抜けなかった」
として猪又を責めるのはさすがに酷である。
また腫瘍が微小であれば、CTの撮影範囲に甲状腺が入っていても腫瘍に気付きにくいこともある。
仮に気づいたとしても、まさかこれが原発巣とは思うまい。
何と言っても「原発性肺癌」という病理診断があるからだ。
(もちろん甲状腺腫瘍をしっかり観察するには甲状腺エコーが必要で、今回大門はこれを見て診断している)
私たち臨床医にとっては、顕微鏡で癌細胞そのものを見た病理医の診断が全てである。
「甲状腺乳頭癌は肺癌と生検でも見分けにくい」
という説明だったが、それならこれに気づけなかった病理医の方に落ち度がないか、猪又は後で問い合わせた方が良いだろう。
どっちみち症例報告には顕微鏡の病理写真を載せなくてはならない。
「よく見直したら甲状腺癌でした」だったら論文にできない。
また、大門が甲状腺癌が原発巣であることに気づいたポイントは2つあったと説明される。
それが、
1つは三鴨の嗄声(させい:声がかすれていること)
もう1つは、半年間抗がん剤治療をしたのに腫瘍が小さくならなかったこと
だという。
声がかすれていたのは、声帯を支配する反回神経(はんかいしんけい)が腫瘍の浸潤を受けていたからだ。
反回神経とは、首の両側を通って胸の中に一度入ったあと、Uターンして戻ってきて声帯にたどり着く、という不思議な走行をしているのが特徴。
それが「反回」と呼ばれるゆえんだ。
よって経路が長い分、途中で癌などに障害されやすい。
大門はこの嗄声を見て甲状腺癌を疑ったとのことである。
しかし今回は、縦隔にまで及ぶあれほど大きな肺の腫瘍があるのだ。
肺の腫瘍が反回神経に浸潤していると考えるのが普通である。
反回神経は一度胸の中に入ってからUターンするため、肺癌など胸の中の病気で麻痺が出ることこそが厄介なのである。
猪又が仮に三鴨の嗄声に気づいていたとしても、肺癌のせいだと考えたはずだ。
また、
「半年間抗がん剤で治療して癌の大きさに変化がない」
というのは、癌を専門にする私たちに言わせれば、
「その抗がん剤はよく効いている」
ということを意味する。
抗がん剤治療を長期間行なっていると、ある時から抗がん剤に耐性を持つがん細胞が現れて、効果がなくなってくることが多い。
こうなると抗がん剤の種類を変える必要があるため、
まだ有効なのか?無効になったのか?
の判断が重要になる。
抗がん剤治療で大切なのは、
「まだ効いているのに効かなくなったと誤るのは絶対に避ける」
ということに尽きる。
限られた手持ちのカードをいかにうまく切っていくかが、患者さんの命をどれだけ延ばせるかに直結するからだ。
そこで、どこの病院でも抗がん剤の効果判定にはRECIST(レシスト)と呼ばれる世界共通のルールを用いている。
(RECIST:Response Evaluation Criteria in Solid Tumors、固形癌の効果判定基準)
このルールでは、
「腫瘍が20%以上大きくなるか、5㎜以上大きくなること」
を「効かなくなっている」と見なすことになっている。
そもそも癌は何も治療しなければどんどん大きくなるもの。
抗がん剤の効果があるからこそ、同じ大きさで維持されているのだ。
さらに言えば、「半年」というのは癌の治療においては短い期間である。
「半年間も」というより「まだ半年間しか」治療していない、というのが正しい考え方で、この間同じ抗がん剤を使用することにも全く違和感はない。
よって今回のケースでは、抗がん剤が効いていると考えて同じ抗がん剤を使っていた猪又を、全く悪いとは思えない。
なぜ私がこうも、傲慢なダメ医者、猪又の肩を持つかというと、現に切除不能の癌の化学療法を行なっている方にとっては、今回のストーリーが「ひとごと」ではなかったと思うからだ。
「私も半年間抗がん剤治療しているのに癌の大きさが変わっていない」
「もしかして誤診では・・・?」
と考えたなら全くの誤解なので、それだけは注意していただきたいと思う。
以上、ほとんどコメディであるドラマに、いつも通り盛大にツッコミを乱れ打ちしたところで今日は終了。
来週もお楽しみに!
最終回まで全話まとめはこちらから!