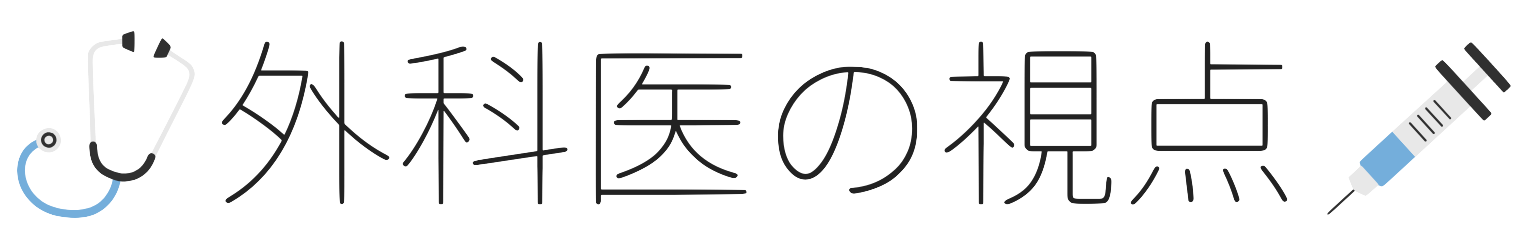私のブログには、将来外科医になりたい、という中高生から色々な質問が寄せられます。
外科に興味がある人にとっては、実際に外科医がどんな風に仕事をしているか、スケジュールをどんな風にマネジメントしているか、知っておきたいでしょう。
私たち外科医としても、今の学生さんが外科医になった時、想像していたのと生活が全く違った、ということがないようきっちり説明しておきたいと思っています。
私はこれまで外科医の仕事について、シリーズで分かりやすくまとめてきました。
緊急手術の前に外科医がやること|医療ドラマで描かれない真実1
手術開始までに手術室で医師が行うこと|医療ドラマで描かれない真実3
今回は少しマニアックに、外科医の朝の忙しさについて書いてみたいと思います。
病院で手術を受ける患者の立場になったことのある人は多いでしょう。
担当の外科医が毎朝病室に入ってきて、せかせかと去っていく姿を見て、ゆっくり話を聞いてくれない、と不満に思った経験もあるかもしれません。
外科医はなぜこんな風に忙しそうにしているのか?
これを知っていただくためにも、内科系の医師とは少し異なる外科医の朝を書いてみます。
外科医特有の朝の忙しさ

私たちは、手術がある日の朝の回診はかなり大急ぎでしなくてはなりません。
何といっても手術日は、「ひとたび手術室に入ったら何時間も出てこられない」という特殊な状況が待っています。
手術室に入る前に、計画的なスケジュール管理が求められるのです。
病院にもよりますが、午前の手術では患者さんが入室するのが8時45分や9時頃に設定されているのが一般的です。
よって、外科医は手術室に遅くとも9時過ぎには到着している必要があります。
麻酔科のスタンスにもよりますが、一般的には、「全身麻酔がかかる前に外科医の誰かが手術室に来ておくように」という暗黙の了解があります(麻酔導入時に患者に何かあった時に担当医が不在では困るため)。
さて、そうなると、9時頃までには自分の担当する入院患者に関わる仕事を全て終えておく必要があります。
全患者が予測通りの経過をたどっていれば問題はありませんが、朝の時点で思わぬ病態の変化が起きていることはしばしばあります。
この場合、朝病棟に行くと看護師から、
「発熱している」
「腹痛を訴えている」
「ドレーン(体の中に入った管)の排液が濁っている」
といった患者さんの変化について報告を受けることになります。
また、早朝に採取した血液検査の結果が出ていて、これを見ると何らかの数値の悪化に気づくこともあるわけです。
こうした変化に対して、逐一適切に対応しなくてはなりません。
タイムリミットは手術室に行く午前9時頃。
これまでに全ての仕事を終えなくてはならない、という厳しい時間管理が求められるわけです。
限られた時間にテキパキとオーダーを

夜間の急変ならともかく、微妙な病態の変化は朝の時点で直接見ないと分かりません。
また、血液検査は通常6時〜7時頃に行い、その結果が8時台に上がってくる、というパターンが一般的です。
早く病院に来ても、血液検査データの変化に気づくのは検査結果が閲覧可能になってから、という律速段階があります。
よって朝の時点で経過を確認し、患者さんを診察し、検査データを見て病態変化を捉え、次々と必要な策を打っていきます。
手術に入る前に、必要な画像検査があればオーダーしておく必要があるし、点滴のメニューを変更する必要があることもあります。
抗菌薬を開始した方がいいということもあるし、血液検査データを見て新たに項目を追加して血液検査を追加する、といったこともあります。
一人の患者さんが相手ならまだいいのですが、複数の患者さんが同時に変化を起こしていた場合、優先順位を即座に判断する必要があります。
外科医の場合、担当患者の多くは術後です。
術後にどういう変化が起こりうるか、どの患者さんにどんな種類の術後合併症が起こりうるか、といったリスクに応じて、優先順位の高い患者さんから対応していかなくてはなりません。
経験上、担当患者が10人を超え始めるところで、こうした対応の難易度がかなり高くなってきます。
おまけに、途中で別の病棟や外来から別の要件で電話がかかってくることもあり、回診が中断されることもあります。
こんな状況だと、当然スケジュール管理を超える量の仕事が発生し、手術開始までに手に負えないこともあります。
手術室に向かう前に全ての仕事が終えられない、という可能性があれば、それを早めに判断し、その日に手術がない人に仕事を引き継ぐ、といったことも要求されます。
もちろん引き継ぐ相手はその患者さんを担当しておらず、これまでの経過を知らないため、短時間にうまく申し送るためのプレゼン力も問われます。
ここできっちりプレゼンできないと、患者さんへの対応が不十分となり、患者さんに不利益を引き起こします。
外科系病棟での患者さんとのトラブルの原因は、ここの不適切な申し送りにあることが実際しばしばあります。
こうした対応を全て終えることができれば、ようやく手術室に向かうことができます。
なお、自分の手術が午後開始のものであった場合は、こうしたスピード感はそれほど要求されません。
午前にどんな手術が行われているかにもよりますが、たいてい手術室に向かうまでに数時間の猶予があるため、患者さんの病態変化にも落ち着いて対応していくことができます。
もちろん手術がない日も同じです(外来がある日はまた別の忙しさがありますが)。
日によって、朝の忙しさは随分違います。
とにかく手術の日の朝は大変です。
もし、担当の医師が病室に訪問し、大して話もせずにせかせかと出て行ってしまったら、それはこういう日なのかもしれません。
もちろん外科医も患者さんに不快な感情を抱かせないよう努力する必要がありますが、どうしても難しい日もあります。
何とかご容赦くだされば、と思っています。
こちらもお読みください。
 外科医だけでは手術できない理由|医療ドラマでは描かれない真実5
外科医だけでは手術できない理由|医療ドラマでは描かれない真実5