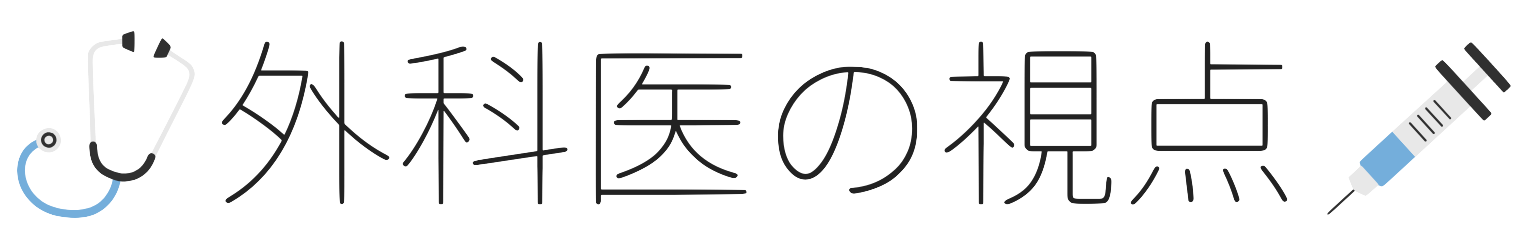胃潰瘍、十二指腸潰瘍の最大の原因は何だと思いますか?
ストレス?お酒?食べすぎ?
いいえ、そのいずれでもありません。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍の原因の95%以上は、ピロリ菌感染か、痛み止めのどちらかだとされています。
ここで言う「痛み止め」とは、ロキソニンやイブプロフェン、ボルタレンなどの「非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)」と呼ばれる解熱鎮痛薬のことです。
「痛み止めが胃を荒らす」という事実を、何となく習慣的に知っている人は多いはずです。
ではどうすれば治療できるでしょうか?
その方法はもちろん、ピロリ菌の除菌か、解熱鎮痛薬の中止です。
非常にシンプルですね。
そう考えれば、慢性的な胃の症状がある場合、医師の診察を受けずに市販の胃薬や漢方薬を繰り返し内服し続けるのは得策ではない、ということが分かります。
ただ、「ピロリ菌の除菌」と言われても何のことかさっぱりわからない、という人もいるでしょう。
また、関節リウマチや変形性関節症などの持病で、痛み止めをやめられない人もいるでしょう。
鎮痛薬だけでなく、同じ成分の抗血小板剤(アスピリン、バファリン、バイアスピリンなど血を固まりにくくする薬)にも同様のリスクがありますが、他の病気でこれらを中止できない人もいます。
その場合はどうすればよいでしょうか?
今回はこうした内容も含めて説明します。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍はあわせて「消化性潰瘍」と呼びます。
今回は「消化性潰瘍診療ガイドライン」の情報をもとに、消化性潰瘍について詳しく解説します。
難しい話は全くありませんのでご安心ください。
目次
消化性潰瘍ってどんな病気?

消化性潰瘍は、胃液に含まれる胃酸と胃の消化酵素により、胃や十二指腸表面の粘膜が傷害されることで起こる病気です。
胃酸は強い酸性環境を作って、食べたものに含まれる細菌やウイルスを殺す働きがあります。
消化酵素(ペプシノーゲンなど)は、食べたもの(主にタンパク質)を分解し、消化するのに役立っています。
これらの強い作用をもつ胃液が、胃や十二指腸の壁に直接かかると傷んでしまうため、通常粘膜の表面は特殊な防御機構によって守られています。
例えば、プロスタグランジンと呼ばれる物質は胃の粘膜を保護する働きがあります。
ところが、この攻撃機構と防御機構のバランスが崩れた時、胃の壁に潰瘍(かいよう)ができてしまいます。
潰瘍とは、表面をおおう粘膜がなくなって壁がえぐれた状態のことです。
口の中の潰瘍である「口内炎」をイメージしてください。
見た目もよく似ています。
胃潰瘍は40〜60歳代の中高年に多く、十二指腸潰瘍は10〜20歳代の若い方に多く見られます。
つまり、消化性潰瘍は幅広い年代に見られる病気です。
何が原因で起こるのか?

消化性潰瘍の主な原因は、ストレスや暴飲暴食ではありません。
前述した通り、ピロリ菌(ヘリコバクターピロリ)による細菌感染か、「非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)」と呼ばれる種類の解熱鎮痛薬が二大成因とされています。
この2つのいずれでもない胃潰瘍は5%以下、十二指腸潰瘍は2%以下とまれです。
この2つ以外には、ストレス、喫煙、クローン病、ゾリンジャーエリソン症候群、サイトメガロウイルスやヘルペスウイルス感染、などが含まれます。
そのため、消化性潰瘍の多くはピロリ菌除菌か解熱鎮痛薬の中止だけで治ります。
このピロリ菌と非ステロイド性抗炎症薬について、まず簡単に説明します。
ピロリ菌感染とは?
ピロリ菌(正確にはヘリコバクターピロリ)は、胃に生息する細菌です。
胃は強い酸性環境なので、多くの細菌は胃の中で生きることができません。
しかしピロリ菌は、尿素からアンモニアを産生する特殊な能力をもっています。
アンモニアはアルカリ性なので、胃酸を中和することにより、ピロリ菌は胃の中で生きることができます。
ピロリ菌によって起こる萎縮性胃炎は、胃癌の原因として広く知られていますが、消化性潰瘍の最大の原因でもあります。
その作用ははっきり知られていませんが、アンモニアが粘膜を傷つけたり、ピロリ菌が産生する活性酸素が粘膜を傷害すると考えられています。
以下の記事もご参照ください。
 胃がんだけじゃない!ピロリ菌が原因になる8つの病気とは
胃がんだけじゃない!ピロリ菌が原因になる8つの病気とは
非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)とは?
非ステロイド性抗炎症薬は、ロキソニン(ロキソプロフェン)、イブプロフェン、ボルタレン(ジクロフェナク)、ピロキシカム、セレコックス(セレコキシブ)などの薬のことです。
これらの薬は、市販の痛み止めや解熱剤、風邪薬にも多く含まれています。
「解熱鎮痛薬」ですので、同じ薬に「鎮痛薬(痛み止め)」と「解熱薬(熱冷まし)」の両方の効果があります。
ボルタレンには座薬もありますが、内服薬でも座薬でも消化性潰瘍のリスクに差はありません(座薬なら潰瘍が起こりにくいということはありません)。
一方、セレコックスは消化性潰瘍の副作用を減らすことを目標に創薬されているため、作用が他のものとやや異なります。
同じ非ステロイド性抗炎症薬でも、消化性潰瘍の発生率は最も低いのが特徴です。
非ステロイド性抗炎症薬は、低用量で用いると解熱鎮痛作用がなくなり、血を固まりにくくする効果が現れます(血小板を阻害します)。
アスピリンやバイアスピリンなどが、その目的で用いる抗血小板剤です。
心筋梗塞や脳梗塞になった方などが多く内服しています。
成分は同じですから、消化性潰瘍のリスクがあります。
これらの薬は、胃の粘膜を保護するプロスタグランジンの産生を抑制します。
胃の防御機構が弱まることが、消化性潰瘍の原因になってしまうということです。
一方、同じ解熱鎮痛薬であるアセトアミノフェン(カロナール、アルピニー、アンヒバ、ピリナジン)は、これに含まれない全く別の種類の薬です。
小児でも安全に用いることのできる薬で、消化性潰瘍は起こしません。
解熱鎮痛薬の種類と副作用については以下にまとめていますので、あわせてお読みください。
 飲みすぎ危険?痛み止めと解熱剤の種類と4つの副作用
飲みすぎ危険?痛み止めと解熱剤の種類と4つの副作用
どんな症状があるのか?

消化性潰瘍の症状には以下のようなものがあります。
胃の痛み
胃の痛み、つまりみぞおち(心窩部)の痛み(鈍痛)が最も多く現れます。
胃潰瘍は食後に痛むことが多く、十二指腸潰瘍は空腹時や夜間に痛むことが多いとされています。
胸焼け
胸焼けや呑酸(げっぷのように酸っぱいものが上がってくる)といった症状を起こします。
人によってはこれを、胃もたれや吐き気ととらえる人もいます。
食欲がなくなり、嘔吐することもあります。
吐血・下血
消化性潰瘍から出血すると、血を吐いたり(吐血)、下血をしたりします。
「下血」とは、真っ黒な便(タール便)が出ることです。
黒色便は、胃や十二指腸からそれなりの量の出血があることを意味します。
すぐに受診が必要です。
特に大量の黒色便が出た場合は、緊急内視鏡検査で止血処置をしなければ命の危険があります。
なお、赤い血液(鮮血)が出る「血便」は、下部消化管(大腸や直腸)からの出血であることが一般的です。
以下の記事もご参照ください。
 病院に行くべき血便(鮮血便)|原因となる病気、何科にかかるか?
病院に行くべき血便(鮮血便)|原因となる病気、何科にかかるか?
無症状
消化性潰瘍があるのに全く症状がない人もいます。
特に、非ステロイド性抗炎症薬が原因で起こる消化性潰瘍は、その半数近くが無症状です。
非ステロイド性抗炎症薬が含まれた痛み止めや解熱剤は、ドラッグストアでも簡単に手に入ります。
症状がなくても、頭痛や腰痛、関節痛などで漫然と痛み止めを飲み続けている人は要注意です。
以下の記事もご参照ください。
 市販の胃薬に頼るとなぜ危険?胃薬の種類と安全な使い分け・選び方
市販の胃薬に頼るとなぜ危険?胃薬の種類と安全な使い分け・選び方
何科に行くべき?

消化性潰瘍の専門は消化器内科です。
次に説明する内視鏡検査やピロリ菌感染の検査は消化器内科の専門です。
内視鏡検査が受けられる消化器内科のクリニックや、病院の消化器内科(消化器科)を受診しましょう。
広告
どんな検査をするの?

消化性潰瘍の検査としては、かつてはバリウムを飲んで行う胃の造影検査(胃透視)が主流でした。
近年では、まず上部消化管内視鏡(胃カメラ)を行うのが一般的です。
造影検査では、小さな消化性潰瘍の診断が難しいからです。
胃カメラは直接胃を観察することができるので、消化性潰瘍だけでなく、胃癌や食道癌など他の病気の診断も可能です。
上述した症状は、消化性潰瘍以外の病気でも起こるため、こうした総合的な検査は大切です。
加えて、上述したピロリ菌感染があるかどうかを調べる検査を行うのが一般的です。
造影検査と胃カメラの違いについては以下の記事もご参照ください。
 胃がん検診で早期発見!胃カメラかバリウムどっちを選ぶべき?
胃がん検診で早期発見!胃カメラかバリウムどっちを選ぶべき?
どのように治療するのか?

以下のどちらが原因なのかが分かれば、治し方は自ずと明らかになります。
きっちり治療すれば、大部分のケースで治癒するとされています。
非ステロイド性抗炎症薬が原因のケース
非ステロイド性抗炎症薬が原因なら、まずこの薬を中止します。
薬の中止のみで潰瘍はほとんど治癒するからです。
ただ、腰痛や関節痛などが強く、痛み止めを中止できない方、心筋梗塞や脳梗塞で抗血小板剤の内服を中止することができない方もいます。
その場合は中止せずに、胃酸分泌を抑える薬「プロトンポンプ阻害薬」を使います。
プロトンポンプ阻害薬は最も強力な薬ですが市販されておらず、病院での処方が必要です。
市販されているヒスタミンH2拮抗薬(ガスターなど)では効き目が弱く、ドラッグストアで簡単に手に入る総合胃腸薬や漢方薬でも、消化性潰瘍は治りません。
ピロリ菌が原因のケース
前述の通り、非ステロイド性抗炎症薬が原因でないなら、大部分はピロリ菌感染が原因です。
ピロリ菌感染の有無を検査し、陽性であれば除菌します。
除菌のみで多くは治癒し、除菌だけで治癒しないものは30%以下です。
治癒しなければ、同じくプロトンポンプ阻害薬を中心とした胃酸を抑える薬による治療を追加します。
きっちり除菌ができれば、潰瘍が再発するのは2%以下です。
ピロリ菌については以下の記事で詳しく解説しています。
 ピロリ菌は胃がんの原因?検査や除菌方法と副作用、感染ルートを解説
ピロリ菌は胃がんの原因?検査や除菌方法と副作用、感染ルートを解説
潰瘍の予防方法は?

非ステロイド性抗炎症薬を継続して内服しなければならない場合は、胃薬を併用して潰瘍を予防します。
時々頓服(とんぷく)として痛み止めを飲む、といった場合は良いですが、毎日継続的に飲む場合は、1ヶ月以内でも潰瘍は発生するため注意が必要です。
投与3か月以内の発生リスクが最も高いとされています。
潰瘍の予防として効果があるのは、プロトンポンプ阻害薬(タケプロン、パリエットなど)、H2拮抗薬(ガスターなど)、プロスタグランジン製剤(サイトテックなど)です。
セルベックス(テプレノン)やムコスタ(レバミピド)などは予防効果が十分証明されていません。
特にリスクが高い方の潰瘍予防として用いるのは適切ではないと考えるべきです。
リスクが高い方とは、消化性潰瘍を経験したことがある方、高齢、副腎皮質ステロイド薬使用者などです。
こういった方は、胃酸分泌を抑える力が最も強いプロトンポンプ阻害薬を予防として用いるのが望ましいとされています。
さまざまな胃薬の名前が出てきて混乱してしまった方がいるかもしれませんね。
胃薬については以下に分かりやすくまとめていますから、合わせてお読みください。
 市販の胃薬に頼るとなぜ危険?胃薬の種類と安全な使い分け・選び方
市販の胃薬に頼るとなぜ危険?胃薬の種類と安全な使い分け・選び方
一方、潰瘍発生リスクの低い非ステロイド性抗炎症薬であるセレコックス(セレコキシブ)を代わりに用いるのも一つの選択肢です。
(セレコックスも市販されていません)
潰瘍を放置するとなぜダメか?

症状がないならそのまま放置してもよいのでは?と思う人がいるかもしれません。
市販の胃薬で症状が軽くなったから様子を見よう、という人もいるかもしれません。
しかし、初期の段階からきっちり治療しなければ、悪化して以下のような重大な病気を引き起こし、命に関わることがあります。
出血
前述の通り消化性潰瘍を放置すると、突然大量の出血を起こすことがあります。
緊急内視鏡によって止血術(止血剤の注射やクリップを用いる)を行わなくてはなりません。
もちろん緊急入院が必要で、完全に止血するまでの期間は絶食です。
内視鏡で止血できない場合は、全身麻酔で手術を行います(病院によってはカテーテル治療で止血することもあります)。
消化性潰瘍からは大量に出血することが多く、輸血が必要になることも少なくありません。
穿孔
潰瘍がどんどん深く掘れていき、そのうち胃や十二指腸の壁を突き破って穴が開きます。
これを「穿孔(せんこう)」と呼びます。
食べたものがお腹の中に漏れ出し、重症の腹膜炎を引き起こします。
熱が出たり、お腹全体にひどい痛みが出て動けなくなります。
早急に治療しなければ命に関わることもあります。
多くの場合、全身麻酔で緊急手術が必要になります。
穴を縫い合わせ、内臓脂肪をかぶせてフタをするような手術です。
私は消化器外科医なので、上述の出血性潰瘍にも、この穿孔性潰瘍にも手術を行ったことは何度もあります。
狭窄
潰瘍をきっちり治さずにいると、その部分の壁が分厚く固くなり、食べ物の通り道が狭くなったり、詰まってしまったりすることがあります。
これを「狭窄(きょうさく)」と呼びます。
こうなると食事が摂れなくなってしまいます。
内視鏡を使ってバルーンで通り道をふくらませて広くしたり、手術を行ったりして治療します。
生活上の注意点

過去に一度消化性潰瘍を経験した人は、再発に注意する必要があります。
ピロリ菌は、きっちり除菌できれば再び陽性化する確率は1%以下とされています。
潰瘍再発の原因として多いのは、高齢、ストレス、喫煙(タバコ)、非ステロイド性抗炎症薬の服用です。
ストレスのない生活を心がけ(難しいと思いますが)、禁煙しましょう。
また痛み止めを内服するときは自己判断で薬局で購入することはせず、必ず医師に相談しましょう。
食生活上の注意としては、消化の良い食事を心がけ、お酒の飲みすぎ、食べ過ぎは控えましょう。
消化性潰瘍について、十分に理解できましたでしょうか?
胃潰瘍、十二指腸潰瘍は誰でも知っているありふれた病気ですが、その原因や治療についてはあまり知られていません。
自己判断で不適切な治療を続け、重大な病気を引き起こすことのないよう注意しましょう。
(参考文献)
消化性潰瘍診療ガイドライン2015/日本消化器病学会
専門医のための消化器病学 第2版/医学書院